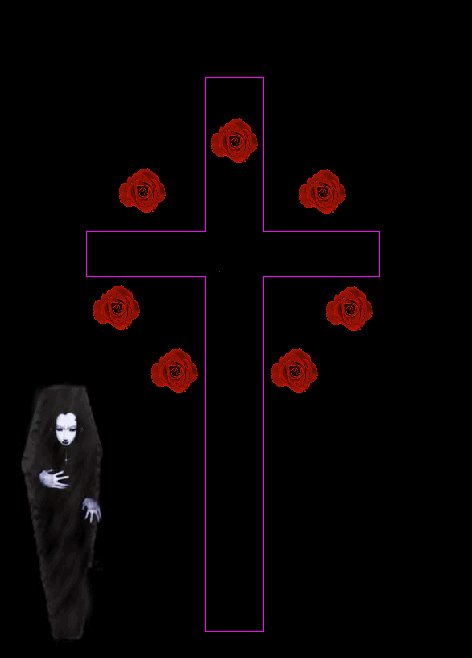ニーチェは唯物論に感情移入した最後の巨人である
ワーグナーの芸術作品をバイロイトで体験したとき、彼の気持ちは離れた。いや、気持ちが離れた、と言うべきではない。彼はこ
れまで、ワーグナーを正しく見たことがなかったのである。彼は自分が未来の理想として夢想したものを、ワーグナーのなかに見
ていたのである。
れまで、ワーグナーを正しく見たことがなかったのである。彼は自分が未来の理想として夢想したものを、ワーグナーのなかに見
ていたのである。
ニーチェは、「私は誤って見ていた」と思った。ニーチェは、若かったころのニーチェから離れたのである。彼はワーグナーに対して
よりも、ワーグナー信奉者だった若いころの自分に対して、激しい言葉を投げかけた。人間は本来、他人の敵にはなれない。人
間は自分自身の敵にしかなれない。「私は青年期の理想すべてが恥ずかしい」と、彼は感じた。彼の世界観は崩れていった。
よりも、ワーグナー信奉者だった若いころの自分に対して、激しい言葉を投げかけた。人間は本来、他人の敵にはなれない。人
間は自分自身の敵にしかなれない。「私は青年期の理想すべてが恥ずかしい」と、彼は感じた。彼の世界観は崩れていった。
なにか他のものを、彼は探さねばならなかった。それが「新しい啓蒙」になった。彼はかつて拒否したものに、いまや生命と心魂
を吹き込もうとする。科学が取り扱っている死んだ素材から、彼は生命を燃え上がらせようとした。いまや彼は、誕生と死を永遠
に過ぎ行く形姿、外的形態を学ぶ。
を吹き込もうとする。科学が取り扱っている死んだ素材から、彼は生命を燃え上がらせようとした。いまや彼は、誕生と死を永遠
に過ぎ行く形姿、外的形態を学ぶ。
人間は三重の世界のなかに生きている、という神智学的な真理を把握すべきである。「誕生と死に屈する、発生し、過ぎ去り、
新たに現れる外的形姿は、生命のなかを形態から形態へと移り行く」。こうして、生命は心魂を表現する。心魂は、新たな形態
のなかに再誕するために、いまの形態を突き破る。そして、人は第三のものを把握する。「さまざまな段階における意識」であ
る。それぞれの石、それぞれの植物が意識を有し、もっと高次の段階で、それぞれの人間が意識を持っている。
新たに現れる外的形姿は、生命のなかを形態から形態へと移り行く」。こうして、生命は心魂を表現する。心魂は、新たな形態
のなかに再誕するために、いまの形態を突き破る。そして、人は第三のものを把握する。「さまざまな段階における意識」であ
る。それぞれの石、それぞれの植物が意識を有し、もっと高次の段階で、それぞれの人間が意識を持っている。
つまり、私たちは世界のなかで三つのものを有する。「形態・生命・意識」である。この三つは、身体の世界、心魂の世界、精神
の世界を表現する。
の世界を表現する。
この叡智がしだいに、ふたたび世界に開かれるだろう。これは、原初の密儀の叡智でもある。この叡智をニーチェは心のなかで
漠然と予感していたが、明瞭に表現することはできなかった。そのために彼は悩み、その叡智を私たちの文化から出現すべき
新しい生命として待望していた。
漠然と予感していたが、明瞭に表現することはできなかった。そのために彼は悩み、その叡智を私たちの文化から出現すべき
新しい生命として待望していた。
いま、彼は自然科学に取り組む。生命のなかに生きていて、高次の形姿へと上昇していくのが意識である。それが世界の歩み
である。それを彼は知らなかった。意識は引き出す価値のあるものを形態から取り出して、高次の形態にもたらす。このようにし
て、形態から形態へ、生命段階から生命段階へと事物は進化する。そこで生命はとどまり、形態と形姿は一段高く形成される。
意識が進化し、常に高次の姿をとることを、彼は理解していない。ニーチェは形態を見る。しかし、常に高次の形態のなかに現れ
る動きを、彼は理解しない。
である。それを彼は知らなかった。意識は引き出す価値のあるものを形態から取り出して、高次の形態にもたらす。このようにし
て、形態から形態へ、生命段階から生命段階へと事物は進化する。そこで生命はとどまり、形態と形姿は一段高く形成される。
意識が進化し、常に高次の姿をとることを、彼は理解していない。ニーチェは形態を見る。しかし、常に高次の形態のなかに現れ
る動きを、彼は理解しない。
こうして、彼は事物と存在が回帰するということを洞察したのだが、常に高次の形態のなかに受肉するということを洞察しなかっ
た。だから、彼は「同じものの回帰」を教えたのである。意識がより高次の段階で回帰することを、彼は知らなかった。それは自
然科学の影響を受けた結果である。いまの私たちと同じ姿で、私たちはすでに何度も存在したのだし、これからもそうだろうとい
うのである。意識は同じ形姿、同じ形態のなかに回帰するのではなく、高められた形姿、高められた形態のなかに回帰するとい
うことを知らない思想家に、この永劫回帰の思想が湧き出たのである。これが、ニーチェの発展の第二段階である。
た。だから、彼は「同じものの回帰」を教えたのである。意識がより高次の段階で回帰することを、彼は知らなかった。それは自
然科学の影響を受けた結果である。いまの私たちと同じ姿で、私たちはすでに何度も存在したのだし、これからもそうだろうとい
うのである。意識は同じ形姿、同じ形態のなかに回帰するのではなく、高められた形姿、高められた形態のなかに回帰するとい
うことを知らない思想家に、この永劫回帰の思想が湧き出たのである。これが、ニーチェの発展の第二段階である。
第三段階では、ニーチェの心魂のなかに精神的な生命はあったが、その生命を単なる「形態の世界観」においては取り出すこと
ができなかった。自分には存在の高次領域が閉じられている、ということを彼は知らなかった。しかし、彼のなかには存在の高
次領域への強い衝動が生きていた。人間は形姿に関しては、動物から人間へと進化した。この進化は終了していない。虫が人
間へと進化したように、人間はさらに進化してしなければならない。
ができなかった。自分には存在の高次領域が閉じられている、ということを彼は知らなかった。しかし、彼のなかには存在の高
次領域への強い衝動が生きていた。人間は形姿に関しては、動物から人間へと進化した。この進化は終了していない。虫が人
間へと進化したように、人間はさらに進化してしなければならない。
こうして、超人の理念が彼に現れた。超人とは、人間が将来なるものである。超人を神秘的な理念と比較すると、両者が隣接し
ているのが分かるだろう。私たちのなかでも示される人間本性の衝動は、霊化の衝動である。人間はすでに今、心魂の土台
に、未来の世界から下ってきた神人を見出すことができる。この神人がニーチェには、努力して到達すべき大きな精神的理想と
思えた。
ているのが分かるだろう。私たちのなかでも示される人間本性の衝動は、霊化の衝動である。人間はすでに今、心魂の土台
に、未来の世界から下ってきた神人を見出すことができる。この神人がニーチェには、努力して到達すべき大きな精神的理想と
思えた。
たんに形態と形姿ではなく、生命と意識、心魂と精神も考察すると、超人の本当の姿が現れる。超人は存在の高次領域に突進
する全人である。ニーチェにはこの思想が萌芽として存在していたが、彼は自然科学者の言葉でしか、それを表現できなかっ
た。人間は何千もの形姿を通過して進化してきた。同様に、人間は高次の形姿の超人へと進化するにちがいない。
する全人である。ニーチェにはこの思想が萌芽として存在していたが、彼は自然科学者の言葉でしか、それを表現できなかっ
た。人間は何千もの形姿を通過して進化してきた。同様に、人間は高次の形姿の超人へと進化するにちがいない。
ニーチェは『悲劇の誕生』を書いたとき、ギリシア密儀の扉の前、ディオニュソス神殿の扉の前に立っていた。しかし、彼は入り口
を開けることができなかった。彼はさらに格闘して、『ツァラトゥストラはこう語った』を書いた。彼はもう一度、神殿の前に立ち、そ
の扉を開けることができなかったのである。これが彼の人生、彼の運命の悲劇である。
を開けることができなかった。彼はさらに格闘して、『ツァラトゥストラはこう語った』を書いた。彼はもう一度、神殿の前に立ち、そ
の扉を開けることができなかったのである。これが彼の人生、彼の運命の悲劇である。
個人として、時代とともに感じる自我、時代とともに苦しむ自我として心魂的・精神的なものに対峙すると、その自我には特別の
ことが起こる。精神ゆたかな自我が自分には開かれぬ謎の扉の前に立つとき、何がその自我に生じるか、アストラル界(心魂の
世界)の現象を知っている者には分かる。問いを発すると、心魂的・精神的世界のなかで、その問いの影のごときものが心魂を
追跡する。唯物論的に思考する人には変だと思われるだろう。
ことが起こる。精神ゆたかな自我が自分には開かれぬ謎の扉の前に立つとき、何がその自我に生じるか、アストラル界(心魂の
世界)の現象を知っている者には分かる。問いを発すると、心魂的・精神的世界のなかで、その問いの影のごときものが心魂を
追跡する。唯物論的に思考する人には変だと思われるだろう。
しかし、キリスト教がどのように進化していくかを知らない者、私たちの哲学、今日の唯物論の前に立って、新しいディオニュソス
を切望しながらもディオニュソスを生み出すことのできない者は、過去の影の前に立っているようなものだ。そのように、アストラ
ル界でニーチェに、キリストの姿のそばにアンチクリスト、道徳家の姿のとなりに不道徳家が現れた。彼が知った現代の哲学の
かたわらに、それを否定するものがあらわれた。それが、彼の自我を追跡し、彼を苦しめたものであった。
を切望しながらもディオニュソスを生み出すことのできない者は、過去の影の前に立っているようなものだ。そのように、アストラ
ル界でニーチェに、キリストの姿のそばにアンチクリスト、道徳家の姿のとなりに不道徳家が現れた。彼が知った現代の哲学の
かたわらに、それを否定するものがあらわれた。それが、彼の自我を追跡し、彼を苦しめたものであった。
ニーチェの最終期の著作、『権力への意志』と『アンチクリスト』を読んでみよう。そこでは、彼特有のニヒリズムで、キリスト教・哲
学が批判されている。これらのものから彼は抜け出られない。善悪から抜け出られず、カルマを認識しようとしない、私たちの時
代の道徳が彼を妨げる。最後になって彼には、永遠に同じ形姿が再帰し、形姿が永遠に交替するように思われた。
学が批判されている。これらのものから彼は抜け出られない。善悪から抜け出られず、カルマを認識しようとしない、私たちの時
代の道徳が彼を妨げる。最後になって彼には、永遠に同じ形姿が再帰し、形姿が永遠に交替するように思われた。
第四の作品は、最後まで書かれなかった。その作品は『ディオニュソス、あるいは永劫回帰の哲学』という題にしよう、と彼は思
っていた。こうして、超人に向けての孤立した自我の衝動だけが残った。
っていた。こうして、超人に向けての孤立した自我の衝動だけが残った。
ニーチェが人間の自己のなかを覗き込み、神的な人間を認識していたら、彼が熱望していたものがつかめていただろう。しかし、
それは彼には到達不可能に思われた。それは、その内容を把握しようとする、彼の内面の強力な衝動でしかなかった。それを
彼は、力への意志、超人への努力と名付けた。彼は『ツァラトゥストラはこう語った』のなかで、心魂を高め、心魂を明るくし、また
心魂を焼き尽くす、しばしば逆説的な叙情詩的表現を用いた。
それは彼には到達不可能に思われた。それは、その内容を把握しようとする、彼の内面の強力な衝動でしかなかった。それを
彼は、力への意志、超人への努力と名付けた。彼は『ツァラトゥストラはこう語った』のなかで、心魂を高め、心魂を明るくし、また
心魂を焼き尽くす、しばしば逆説的な叙情詩的表現を用いた。
それは神人・叡智への現代人の叫びである。しかし、その叫びは叡智への意志、力への意志までしか到らない。壮大な叙情詩
が、この衝動から発する。しかし、人間の最も深い内面を把握して高みに導くものは、この衝動から現れない。
が、この衝動から発する。しかし、人間の最も深い内面を把握して高みに導くものは、この衝動から現れない。
ニーチェは唯物論に感情移入した最後の巨人であり、19世紀の唯物論に苦しみ、悲劇的に崩壊した人物である。そして、憧れ
を込めて新しい神秘的な時代を示唆した人物である。
を込めて新しい神秘的な時代を示唆した人物である。
(P138-P142)
ニーチェはある本のなかで、「奮起せよ、人間であれ。歴史を作れ。単に歴史を探索するな。自立して独自に行動する勇気を持
て」と書いている。これも解放の書である。歴史からの解放を急進的に要求する本である。人間の根源的な衝動すべてにとっ
て、歴史的な気分は障害である、と述べられている。
て」と書いている。これも解放の書である。歴史からの解放を急進的に要求する本である。人間の根源的な衝動すべてにとっ
て、歴史的な気分は障害である、と述べられている。
1876年まで、ニーチェはそのようであった。彼は世界のなかで起こっていることから遠く離れていた。彼のエーテル体の可動性
が、そのようなありかたを引き起こした。1876年、ワーグナーが創造の頂点に立ち、彼の心魂のなかに生きるものを外の世界で
実現したとき、ニーチェは「私が目の当たりにしているものは、私のなかに生きているイメージに相応しない」と気づいた。彼は外
的な現実の要求に対する防壁のようなものを有していたので、目の当たりにしているものが彼のなかに生きていたイメージに相
応しなかったのである。彼は内面で形成した表象を外で再確認することができなかった。そこでニーチェは混乱した。
が、そのようなありかたを引き起こした。1876年、ワーグナーが創造の頂点に立ち、彼の心魂のなかに生きるものを外の世界で
実現したとき、ニーチェは「私が目の当たりにしているものは、私のなかに生きているイメージに相応しない」と気づいた。彼は外
的な現実の要求に対する防壁のようなものを有していたので、目の当たりにしているものが彼のなかに生きていたイメージに相
応しなかったのである。彼は内面で形成した表象を外で再確認することができなかった。そこでニーチェは混乱した。
彼は何を見損なったのだろうか。ワーグナーか。そうではない。彼はリヒャルト・ワーグナーを見損なったのではない。彼はリヒャ
ルト・ワーグナーを、客観的にはまったく知らなかったからである。彼は自分がリヒャルト・ワーグナーについて作ったイメージを信
じられなくなったのである。ニーチェは、自分をワーグナーに導いた展望全体を信じられなくなった。
ルト・ワーグナーを、客観的にはまったく知らなかったからである。彼は自分がリヒャルト・ワーグナーについて作ったイメージを信
じられなくなったのである。ニーチェは、自分をワーグナーに導いた展望全体を信じられなくなった。
彼はあらゆる理想主義を信じられなくなった。理想的なワーグナーとともに、人類が紡ぎ出したあらゆる理想が、彼から失われた
のである。彼のなかに「理想主義、ならびに精神的なものについての熟考はすべて嘘であり、虚偽であり、幻想である」という感
情が発生した。人間は現実についてイメージを作ることによって、現実について思い違いをする。ニーチェは自分自身に苦しみは
じめた。
のである。彼のなかに「理想主義、ならびに精神的なものについての熟考はすべて嘘であり、虚偽であり、幻想である」という感
情が発生した。人間は現実についてイメージを作ることによって、現実について思い違いをする。ニーチェは自分自身に苦しみは
じめた。
いまや彼は精神生活に対立する流れ、実証的な自然科学の分野に没頭する。彼は興味深い人物、道徳的感受と良心の発生
について本を書いたパウル・レーと知り合った。その本は、19世紀後期にとって特徴的な書物である。自然科学を手本として探
求・研究がなされており、道徳的感受と良心の発生を人間の衝動と本能から取り出している。それをパウル・レーは才気あふれ
る筆で書いている。
について本を書いたパウル・レーと知り合った。その本は、19世紀後期にとって特徴的な書物である。自然科学を手本として探
求・研究がなされており、道徳的感受と良心の発生を人間の衝動と本能から取り出している。それをパウル・レーは才気あふれ
る筆で書いている。
ニーチェは、この世界観に熱狂した。「あらゆる幻想が克服された。明白なものだけから人間のいとなみすべてが把握できる。い
まや、あらゆる理想が衝動と本能の仮面だと感じられる」と、彼は思った。箴言の形で出版された『人間的な、あまりに人間的
な』のなかで、すべての理想は人間を越えていくものではなく、あまりにも人間的なもの、感情・日常に根差しているということ
を、彼は描こうとした。
まや、あらゆる理想が衝動と本能の仮面だと感じられる」と、彼は思った。箴言の形で出版された『人間的な、あまりに人間的
な』のなかで、すべての理想は人間を越えていくものではなく、あまりにも人間的なもの、感情・日常に根差しているということ
を、彼は描こうとした。
ニーチェはかつて、日常のなかへの道を直接的に見出すことができなかった。彼は人間一般的なものを、実際経験からは知らな
かった。彼は理論から、あらゆる喜びと苦しみを体験しようとした。生活実践も、彼には理論になった。それは『曙光』のなかで、
みごとに表現されている。彼にはすべてが誤っていると思えただけでなく、すべてが氷の上に置かれたように冷たいものになっ
た。
かった。彼は理論から、あらゆる喜びと苦しみを体験しようとした。生活実践も、彼には理論になった。それは『曙光』のなかで、
みごとに表現されている。彼にはすべてが誤っていると思えただけでなく、すべてが氷の上に置かれたように冷たいものになっ
た。
いまや、ニーチェはオイゲン・デューリングの現実哲学を研究することに特別の満足を感じる。彼は現実哲学に熱中するが、現実
哲学のシンパではない。彼は本に多くの書き込みをしている。そして一部は否定的な注釈である。彼は実証的科学に関して述
べられたものを、心魂的に、感情に即して体験しようと試みる。生の道徳を規範にしたがってではなく、出来事にしたがって判断
することを目標にするフランスの著述家たちの本は、彼にとって刺激的だった。それは彼にとって、悲劇になるとともに、至福に
なる。彼がそのすべてを体験したことが重要である。それは彼にとって、その作品を書いた者たちとは別様に作用する。「これら
と、いかに生きるか」と、彼は常に自問しなければならない。
哲学のシンパではない。彼は本に多くの書き込みをしている。そして一部は否定的な注釈である。彼は実証的科学に関して述
べられたものを、心魂的に、感情に即して体験しようと試みる。生の道徳を規範にしたがってではなく、出来事にしたがって判断
することを目標にするフランスの著述家たちの本は、彼にとって刺激的だった。それは彼にとって、悲劇になるとともに、至福に
なる。彼がそのすべてを体験したことが重要である。それは彼にとって、その作品を書いた者たちとは別様に作用する。「これら
と、いかに生きるか」と、彼は常に自問しなければならない。
そのような前提から、意味深い理念が彼に生じた。その理念を見ると、ニーチェは精神科学の門を叩いた、と言わねばならな
い。ディオニュソス的人間について考えることによって、彼は密儀を予感し、精神科学の門を叩いた。その門は、彼には開かれな
かった。その理念の一つがどのように発生したか、証明できる。
い。ディオニュソス的人間について考えることによって、彼は密儀を予感し、精神科学の門を叩いた。その門は、彼には開かれな
かった。その理念の一つがどのように発生したか、証明できる。
デューリングの本『厳密に学問的な世界観と生命形成としての哲学講義』のなかに、注目すべき箇所がある。かつて存在した
のと同じ原子と分子の結合が、いつか同じ形で再来することは可能か、という問いをデューリングは立てようとしている。
のと同じ原子と分子の結合が、いつか同じ形で再来することは可能か、という問いをデューリングは立てようとしている。
かつて私は、三週間ニーチェの蔵書を整頓していたとき、その本のこの箇所に彼が線を引き、所感を書き込んでいるのを見た。
そこから、最初は意識下で、いわゆる永劫回帰の理念が彼のなかで発酵していった。
そこから、最初は意識下で、いわゆる永劫回帰の理念が彼のなかで発酵していった。
彼はこの理念を次第に形成していった。その理念はニーチェの心魂のなかに描き込まれて、彼の信条になった。彼はその理念
に精通し、その理念が彼の悲劇になった。かつて存在したものは、長い時間ののち、細部にいたるまで同じ形で回帰するにち
がいない、ということをその理念は表現している。
に精通し、その理念が彼の悲劇になった。かつて存在したものは、長い時間ののち、細部にいたるまで同じ形で回帰するにち
がいない、ということをその理念は表現している。
私たちは無数の回数、再来するというのである。「いま私が体験している苦悩すべてをもって、私はいつまでも再来する」という
感情は、彼の心魂の悲劇に属するものであった。ニーチェは回帰に関するデューリングの理念をとおして唯物論的な思想家にな
った(デューリング自身は回帰を否定している)。彼にとって、同じものの再来は、唯物論的な理念の帰結にすぎなかった。
感情は、彼の心魂の悲劇に属するものであった。ニーチェは回帰に関するデューリングの理念をとおして唯物論的な思想家にな
った(デューリング自身は回帰を否定している)。彼にとって、同じものの再来は、唯物論的な理念の帰結にすぎなかった。
ニーチェの理念が19世紀の文化の流れから結晶するものを、私たちは見る。不完全なものから完全なものへの進化、単純な生
物から人間への進化をダーウィンは示す。それはニーチェにとって空論ではない。それは彼にとって至福の源泉になる。世界の
進化を見ることによって、彼は満足を感じる。しかし、彼はそこに立ち止まれない。
物から人間への進化をダーウィンは示す。それはニーチェにとって空論ではない。それは彼にとって至福の源泉になる。世界の
進化を見ることによって、彼は満足を感じる。しかし、彼はそこに立ち止まれない。
「人間は生成された。それならば、人間はさらに生成されるべきではないか。不完全な存在が人間へと進化した。進化は人間で
終了すべきなのか。人間は超人への移行段階だ、と見なければならない」と、彼は思う。こうして、彼にとって人間は、虫と超人
とのあいだに架かる橋のようなものになった。
終了すべきなのか。人間は超人への移行段階だ、と見なければならない」と、彼は思う。こうして、彼にとって人間は、虫と超人
とのあいだに架かる橋のようなものになった。
ニーチェは永劫回帰の理念によって、感情と思考のすべてをもって、輪廻転生という精神科学の真理の門前に立った。また、彼
は超人の理念によって、人間の神的な存在の核が各人のなかに生きていることを示す精神科学の門前に立った。人間の神的
な存在の核は、本当に一種の超人である。人間は多くの転生を経て、ますます完全になっていき、高次の存在段階へと上昇す
る。
は超人の理念によって、人間の神的な存在の核が各人のなかに生きていることを示す精神科学の門前に立った。人間の神的
な存在の核は、本当に一種の超人である。人間は多くの転生を経て、ますます完全になっていき、高次の存在段階へと上昇す
る。
感覚的なものの背後を見ると明らかになる、これらの具体的精神科学の秘密について、ニーチェは何も知らなかった。だから、
彼は自分の心魂のなかに生きていたものについて、自我ではなく、単に感情で把握した。私たちをいつも新たな至福で満たすこ
とのできる精神的な事実の記述、惑星進化のなかで人間が段階を上昇していくという事実の記述ではなく、すべてがニーチェに
おいては感情のなかに生きており、それは『ツァラトゥストラはこう語った』のなかで叙情的に表現された。この本は、彼が見るこ
とのできなかったものへの予感を情熱的に叙述している。
彼は自分の心魂のなかに生きていたものについて、自我ではなく、単に感情で把握した。私たちをいつも新たな至福で満たすこ
とのできる精神的な事実の記述、惑星進化のなかで人間が段階を上昇していくという事実の記述ではなく、すべてがニーチェに
おいては感情のなかに生きており、それは『ツァラトゥストラはこう語った』のなかで叙情的に表現された。この本は、彼が見るこ
とのできなかったものへの予感を情熱的に叙述している。
この渇望する心魂は、どのように満足させられるだろうか。精神科学の内容を知ることによってのみ満足するのである。ニーチェ
の心魂は精神科学への憧れに、血を流して死ぬにちがいない。彼が理解することなく手に入れようと格闘していたものを、精神
科学のみが彼に提供できていたのである。
の心魂は精神科学への憧れに、血を流して死ぬにちがいない。彼が理解することなく手に入れようと格闘していたものを、精神
科学のみが彼に提供できていたのである。
『権力への意志』という題にしようとしていた彼の最後の本に、いかに彼の心魂が切望した精神の内実が満たされなかったか
が、はっきりと示されている。精神世界に属している高次の人間について述べる精神科学と、本質的に無内容な権力への意志
とを比べてみよう。権力が何を有するべきかが語られないと、権力というのはまったく抽象的なものである。
が、はっきりと示されている。精神世界に属している高次の人間について述べる精神科学と、本質的に無内容な権力への意志
とを比べてみよう。権力が何を有するべきかが語られないと、権力というのはまったく抽象的なものである。
遺稿『権力への意志』は、ニーチェが素晴らしいと感じた性急な努力が、無益で宿命的なものであることを示している。この未踏
の領域にむけての努力が狂気へと進む、という悲劇が生じる。
の領域にむけての努力が狂気へと進む、という悲劇が生じる。
19世紀の文化がものごとを深く感じる人間をどこに導くかが、ニーチェにおいてはっきりと見られる。19世紀の文化のなかにとど
まっていたために、物質を越えたものについて何かを予感しながら見出すことのできなかった多くの人々は、この文化ゆえに血
を流して死なねばならなかった。だから、ニーチェの悲劇は19世紀の悲劇を示しているのである。
まっていたために、物質を越えたものについて何かを予感しながら見出すことのできなかった多くの人々は、この文化ゆえに血
を流して死なねばならなかった。だから、ニーチェの悲劇は19世紀の悲劇を示しているのである。
ニーチェは、物質的身体のせいでエーテル体がしっかりと結び付いていない人間のみが有する大胆さをもって、『アンチクリスト』
でキリスト教を批判する。そこに、19世紀の悲劇が特に示されている。彼が語るのは、キリスト教にとって辛辣でありながらも尤
もな、非常に印象的な批判である。『アンチクリスト』に書かれていることがらの多くは、本当に一読の価値がある。ニーチェは現
実から精神を探求しようとした。そして、近代のキリスト教の形態のなかには精神を見出せなかった。彼には、あらゆる哲学がニ
ヒリズムに思えた。
でキリスト教を批判する。そこに、19世紀の悲劇が特に示されている。彼が語るのは、キリスト教にとって辛辣でありながらも尤
もな、非常に印象的な批判である。『アンチクリスト』に書かれていることがらの多くは、本当に一読の価値がある。ニーチェは現
実から精神を探求しようとした。そして、近代のキリスト教の形態のなかには精神を見出せなかった。彼には、あらゆる哲学がニ
ヒリズムに思えた。
人類は精神科学をとおして、キリスト教の偉大な衝動と深さを初めて認識する。「いままでキリスト教は、ごく一部分しか認識さ
れていなかった」と言うことができる。この意識をニーチェは持っていなかった。彼はキリスト教を正しく認識しなかった。なぜ、彼
は認識できなかったのだろう。彼は、精神科学の意味における進化の歩みを予感できなかったからである。
れていなかった」と言うことができる。この意識をニーチェは持っていなかった。彼はキリスト教を正しく認識しなかった。なぜ、彼
は認識できなかったのだろう。彼は、精神科学の意味における進化の歩みを予感できなかったからである。
キリスト教の深みに隠れているものが、精神科学をとおして取り出される。ニーチェがキリスト教のなかに見たのは、それとは反
対のものである。それを認識できなかったことで、彼は血を流した。
対のものである。それを認識できなかったことで、彼は血を流した。
ニーチェの苦悩は、生命の源泉への最も深く、最も痛ましい憧れである。精神が物質的身体としっかり結び付いていないことに
よって、彼は自分を苦しめる宇宙の謎を正しく解明するにいたらない。生の問いへの正しい答えは、精神科学によって与えられ
る。そのそばを通り過ぎたことに、彼は気づかなかった。物質的身体という道具が使用不能になったとき、彼はこの道具を投げ
捨てた。思考にとって役に立たなくなった物質的身体を放棄し、その上に漂うのである。
よって、彼は自分を苦しめる宇宙の謎を正しく解明するにいたらない。生の問いへの正しい答えは、精神科学によって与えられ
る。そのそばを通り過ぎたことに、彼は気づかなかった。物質的身体という道具が使用不能になったとき、彼はこの道具を投げ
捨てた。思考にとって役に立たなくなった物質的身体を放棄し、その上に漂うのである。
こうして、彼にまなざしを向ける者に、彼は集中的な思考作業ののちに休息している健康人のように見える。精神的なものを認
識できない今日の唯物論的科学の悲劇全体を体験した者として、彼はベッドに横たわっていた。
識できない今日の唯物論的科学の悲劇全体を体験した者として、彼はベッドに横たわっていた。
(P152-P157)