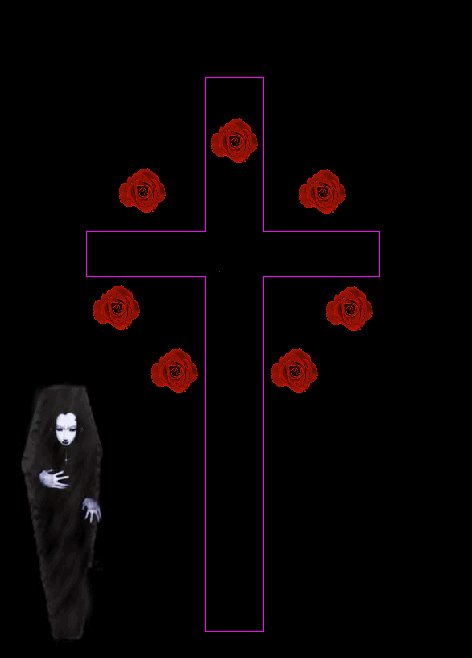光は無限に出ていくのではない
わたしは昔から、光は無限に出ていくという考えは無意味である、と申し上げてきました。光の放散の基盤には弾性がある、と
申し上げてきました。ゴム製のボールを押すと、あるところまでは押せますが、そこからは押し返されます。弾性にとって圧縮に
は終点があり、そこからは押し戻されるのです。光についてもおなじことがいえます。光は無限にでていくのではなく、ある境界
に達すると、ふたたび戻ってきます。
申し上げてきました。ゴム製のボールを押すと、あるところまでは押せますが、そこからは押し返されます。弾性にとって圧縮に
は終点があり、そこからは押し戻されるのです。光についてもおなじことがいえます。光は無限にでていくのではなく、ある境界
に達すると、ふたたび戻ってきます。
光は無限に進むのではなく、ある境界までしか進まず、その境界からふたたび戻ってくるという説は、たとえばイギリスの物理
学者オリヴァー・ロッジが唱えています。精神科学が唱えていることを、物理的な科学が唱えるところにまで、今日ではいたって
いるのです。将来、精神科学が述べていることの詳細にわたるまで、科学が認めるようになるでしょう。
学者オリヴァー・ロッジが唱えています。精神科学が唱えていることを、物理的な科学が唱えるところにまで、今日ではいたって
いるのです。将来、精神科学が述べていることの詳細にわたるまで、科学が認めるようになるでしょう。
十分に考えることができるなら、外界はたんに無限の空間なのではない、と語らねばなりません。無限の空間というのは、一個
の空想です。しかも、把握できない空想です。『わが生涯』第三章のなかに書いたことですが、総合的な新しい幾何学の授業を
受けたときに、まず直線というものを無限に伸びていくものではなく、べつの側から戻ってくるものだと教えられたときに、わたし
は特別大きな印象を受けました。幾何学では、つぎのようにいいます。「右側に無限に遠い点は、左側に無限に遠い点とおなじ
ものである」。このことは算定することができます。円があって、その円のある点から出発すると元のところに戻ってくるというのと
おなじです。あるいは無限の半弧というのは一個の直線である、というのとおなじです。
の空想です。しかも、把握できない空想です。『わが生涯』第三章のなかに書いたことですが、総合的な新しい幾何学の授業を
受けたときに、まず直線というものを無限に伸びていくものではなく、べつの側から戻ってくるものだと教えられたときに、わたし
は特別大きな印象を受けました。幾何学では、つぎのようにいいます。「右側に無限に遠い点は、左側に無限に遠い点とおなじ
ものである」。このことは算定することができます。円があって、その円のある点から出発すると元のところに戻ってくるというのと
おなじです。あるいは無限の半弧というのは一個の直線である、というのとおなじです。
しかし、わたしに大きな印象を与えたのは、そのようなありきたり類推ではなく、左側に無限に遠い点は右側に無限に遠い点と
おなじであるということが、ほんとうに計算によって証明できることでした。正確に思考する人間は、そのような類推を無視しま
す。だれかがある方向にむかって走りはじめたなら、ある時間ののちに反対側からやってくることになります。このようなことは、
物理的思考にはグロテスクなものに見えます。物質的思考を脱却すると、これは現実になります。世界は無限ではなく、物質界
として目の前にあるように、限られたものだからです。ですから、「植物および人間におけるエーテル的なものについて語るなら、
エーテルの境界に行かねばならない」と、いうことができます。
おなじであるということが、ほんとうに計算によって証明できることでした。正確に思考する人間は、そのような類推を無視しま
す。だれかがある方向にむかって走りはじめたなら、ある時間ののちに反対側からやってくることになります。このようなことは、
物理的思考にはグロテスクなものに見えます。物質的思考を脱却すると、これは現実になります。世界は無限ではなく、物質界
として目の前にあるように、限られたものだからです。ですから、「植物および人間におけるエーテル的なものについて語るなら、
エーテルの境界に行かねばならない」と、いうことができます。
しかし、動物および人間のなかのアストラル的なものを説明しようと思うなら、空間のなかにあるものすべてから出ていかねばな
りません。時間のなかを散策しなければなりません。同時性から去って、時間のなかに進まねばなりません。
りません。時間のなかを散策しなければなりません。同時性から去って、時間のなかに進まねばなりません。
そして、人間にいたります。時間のなかに入ると、すでに二重の方法で、物質的なものを越えます。動物を把握するには、すで
に時間のなかを進まねばなりません。この思考方法を抽象的にではなく、具体的に継承しなければなりません。
に時間のなかを進まねばなりません。この思考方法を抽象的にではなく、具体的に継承しなければなりません。
人間は、「太陽が光を送ると、光は無限に進む」と、考えるのではないでしょうか。人々はもはやそのような思考方法を捨て、光
は終点にいたり、ふたたび帰ってくるということを知っている、とオリヴァー・ロッジは述べています。太陽はあらゆる方向から、自
分の光をふたたび受け取るのです。変化したべつの形ではあっても、自分の光をふたたび受け取るのです。(P24-P27)
は終点にいたり、ふたたび帰ってくるということを知っている、とオリヴァー・ロッジは述べています。太陽はあらゆる方向から、自
分の光をふたたび受け取るのです。変化したべつの形ではあっても、自分の光をふたたび受け取るのです。(P24-P27)
ニーチェの永劫回帰思想
わたしは、つぎのような経験をしたことがあります。わたしはニーチェの未発表原稿の整理をしていて、永劫回帰に関する文章を
手にしていました。ニーチェの自筆原稿は読みやすいものではありません。わたしは永劫回帰について書かれたものを手にし
て、「ニーチェの永劫回帰説の由来となったものがある」と、思いました。わたしは当時、エリザベート・フェルスター=ニーチェと
知り合いでした。わたしたちはその原稿を持って、ニーチェ書庫から図書館に行き、デューリングの『現実哲学』を調べました。そ
こに、わたしたちは永劫回帰の思想を発見したのです。
手にしていました。ニーチェの自筆原稿は読みやすいものではありません。わたしは永劫回帰について書かれたものを手にし
て、「ニーチェの永劫回帰説の由来となったものがある」と、思いました。わたしは当時、エリザベート・フェルスター=ニーチェと
知り合いでした。わたしたちはその原稿を持って、ニーチェ書庫から図書館に行き、デューリングの『現実哲学』を調べました。そ
こに、わたしたちは永劫回帰の思想を発見したのです。
ニーチェは非常に多くの理念を、「反対理念」として作り上げました。それは、すぐに調べることができました。ニーチェ文庫にあっ
た『現実哲学』を取り出して、ページを繰ってみました。「世界の物質的事実の現実的で事実に即した認識からいえば、かつて
存在した事物や星位が再来するのは不可能である」と、書かれています。
た『現実哲学』を取り出して、ページを繰ってみました。「世界の物質的事実の現実的で事実に即した認識からいえば、かつて
存在した事物や星位が再来するのは不可能である」と、書かれています。
デューリングは、同一物の再来は不可能であるということを証明しようとしたのです。そのページの余白にニーチェは「まぬけ」と
書き込んでいました。ニーチェは、本の余白を利用して、反対概念を形成していたのです。
書き込んでいました。ニーチェは、本の余白を利用して、反対概念を形成していたのです。
そのような書き込みがあったのです。天才的な方法でニーチェの理念に変化していったものを、デューリングの著作のなかに多
く見出すことができます。わたしはニーチェに反対するつもりはないのですが、事実はそうなのです。(P165-P166)
く見出すことができます。わたしはニーチェに反対するつもりはないのですが、事実はそうなのです。(P165-P166)
ニーチェ・フランシスコ会修道士
わたしは、フリードリッヒ・ニーチェの運命の関連に大きな興味を持っています。わたしの人生はわたしを、この人物に導いたから
です。わたしはニーチェ問題を、あらゆる面から考察しました。わたしはニーチェについて多くのことを述べ、フリードリッヒ・ニーチ
ェをあらゆる側から考察しました。
です。わたしはニーチェ問題を、あらゆる面から考察しました。わたしはニーチェについて多くのことを述べ、フリードリッヒ・ニーチ
ェをあらゆる側から考察しました。
わたしが彼に会ったのは一度だけです。1890年代にナウムブルクで会ったのですが、そのとき彼はすでに重い精神病にかか
っていました。午後2時半ごろ、彼の妹がわたしを彼の部屋に案内してくれました。彼は寝椅子に横たわっていて、彼の目は人
が入ってきたことに気づかず、無関心でした。美しい、芸術的な額が注意を引きました。目が無関心であるにもかかわらず、狂
人が目のまえにいるという感じではなく、午前中集中的に魂のなかで精神的に活動して、昼食をとり、休息しながら、午前中魂
のなかでおこなったことについて思索しているように感じられました。霊的に見ると、そこには物質体とエーテル体しかなく、心魂
と精神はすでに外にあって、太糸で身体につながっていました。すでに死が近いのですが、身体組織が健康なので、完全な死
にはいたっていないのでした。完全に破壊された神経−感覚組織はもはやアストラル体と自我を保持することができないのです
が、非常に健康な新陳代謝−律動組織が飛び去ろうとするアストラル体と自我をつかんでいるのでした。「ほんとうのニーチェ
は、彼の頭の上に漂っている。下方にある身体は、心魂に去られて死を迎えてもよいのだが、非常に健康な新陳代謝−律動組
織によって身体が心魂に結びついているので、まだ死がやってこないのだ」という印象をわたしは持ちました。(P204-P205)
っていました。午後2時半ごろ、彼の妹がわたしを彼の部屋に案内してくれました。彼は寝椅子に横たわっていて、彼の目は人
が入ってきたことに気づかず、無関心でした。美しい、芸術的な額が注意を引きました。目が無関心であるにもかかわらず、狂
人が目のまえにいるという感じではなく、午前中集中的に魂のなかで精神的に活動して、昼食をとり、休息しながら、午前中魂
のなかでおこなったことについて思索しているように感じられました。霊的に見ると、そこには物質体とエーテル体しかなく、心魂
と精神はすでに外にあって、太糸で身体につながっていました。すでに死が近いのですが、身体組織が健康なので、完全な死
にはいたっていないのでした。完全に破壊された神経−感覚組織はもはやアストラル体と自我を保持することができないのです
が、非常に健康な新陳代謝−律動組織が飛び去ろうとするアストラル体と自我をつかんでいるのでした。「ほんとうのニーチェ
は、彼の頭の上に漂っている。下方にある身体は、心魂に去られて死を迎えてもよいのだが、非常に健康な新陳代謝−律動組
織によって身体が心魂に結びついているので、まだ死がやってこないのだ」という印象をわたしは持ちました。(P204-P205)
ニーチェの個体が身体の上に漂っている衝撃的な姿を目にすると、彼の著作に対して、「彼の著作を読むと、ニーチェは書いてい
たとき、けっして完全に身体のなかにいなかったという印象を受ける。彼は、いつも身体の外にいたかのように思われる」と、い
わざるをえません。事実、彼は座って書いたのではなく、歩きながら書きました。とくに彼が身体の外にいたと強く感じられるの
は、『ツァラトゥストラはこう語った』第四部です。「これは身体が正常な状態で書かれたのではない。身体がもはや正常ではな
く、心魂が身体の外にあるときのみ、このようなものは書ける」という感情をわたしは持ちます。
たとき、けっして完全に身体のなかにいなかったという印象を受ける。彼は、いつも身体の外にいたかのように思われる」と、い
わざるをえません。事実、彼は座って書いたのではなく、歩きながら書きました。とくに彼が身体の外にいたと強く感じられるの
は、『ツァラトゥストラはこう語った』第四部です。「これは身体が正常な状態で書かれたのではない。身体がもはや正常ではな
く、心魂が身体の外にあるときのみ、このようなものは書ける」という感情をわたしは持ちます。
精神的生産においてニーチェは自分の身体を置き去りにした、という感情をわたしたちは持ちます。彼は日常の習慣において
も、ついにはそうなりました。彼はとくにクロラールを好み、身体から離れる気分を味わいました。心魂の気分のなかの、身体か
ら離れたいという憧憬をとおして身体は病気になり、たとえば頭痛が長期にわたってつづきました。
も、ついにはそうなりました。彼はとくにクロラールを好み、身体から離れる気分を味わいました。心魂の気分のなかの、身体か
ら離れたいという憧憬をとおして身体は病気になり、たとえば頭痛が長期にわたってつづきました。
これらすべてが、19世紀末におけるニーチェのイメージを与えます。ニーチェは狂気にいたり、ついには自分がだれであるかわ
からなくなりました。デンマークの文芸評論家ゲオルグ・ブランデスにあてた手紙に、彼は「十字架に懸かった者」とサインした
り、自分を自分の外にいる人のように客観的に見たり、自分をイタリアのポー川を散歩する神だと思って、「ディオニュソス」とサイ
ンしたりしました。精神的な生産活動における身体からの遊離が、ニーチェとしての人生における特徴でした。
からなくなりました。デンマークの文芸評論家ゲオルグ・ブランデスにあてた手紙に、彼は「十字架に懸かった者」とサインした
り、自分を自分の外にいる人のように客観的に見たり、自分をイタリアのポー川を散歩する神だと思って、「ディオニュソス」とサイ
ンしたりしました。精神的な生産活動における身体からの遊離が、ニーチェとしての人生における特徴でした。
内的−イマジネーション的に進んでいくと、それほど過去にはさかのぼらない前世に導かれていきます。代表的な人物の多くに
おいて特徴的なのは、彼らの前世がはるかな過去にさかのぼるものではなく、比較的近代にあるということです。ニーチェはか
つて禁欲的なフランシスコ会修道士で、徹底的に自分を痛めつけました。フランシスコ会修道院の修道服に身を包んだ人物が
何時間も祭壇のまえでひざまずいて祈り、非常な苦行をしました。自分が課した苦痛をとおして、思いが自分の身体に強く集ま
ります。苦痛を感じているとき、人間は特別肉体を意識します。アストラル体が苦痛を感じている肉体に浸透しようと強く望むか
らです。救済を願って身体を痛めたことによって、魂はつぎの人生においては身体のなかにもう入りたくないと思うようになりまし
た。
おいて特徴的なのは、彼らの前世がはるかな過去にさかのぼるものではなく、比較的近代にあるということです。ニーチェはか
つて禁欲的なフランシスコ会修道士で、徹底的に自分を痛めつけました。フランシスコ会修道院の修道服に身を包んだ人物が
何時間も祭壇のまえでひざまずいて祈り、非常な苦行をしました。自分が課した苦痛をとおして、思いが自分の身体に強く集ま
ります。苦痛を感じているとき、人間は特別肉体を意識します。アストラル体が苦痛を感じている肉体に浸透しようと強く望むか
らです。救済を願って身体を痛めたことによって、魂はつぎの人生においては身体のなかにもう入りたくないと思うようになりまし
た。
このような運命的な関連があるのです。一連の地上生について、通常の思い込みをもって臆断することはできません。臆断する
と、たいてい間違います。しかし、正しいことがわかると、人生が解明されます。(P204-P210)
と、たいてい間違います。しかし、正しいことがわかると、人生が解明されます。(P204-P210)
ニーチェの精神遍歴
ニーチェの生涯は、三つの時期にはっきり分かれます。第一期は、若いニーチェが『音楽の精神からの悲劇の誕生』を書き、ギリ
シアの密儀から音楽が発生し、悲劇が音楽から生まれたことに熱狂したときから始まります。その気分から、『信仰者であり著
述家であるダヴィッド・フリードリッヒ・シュトラウス』『人生にとっての歴史の効用と害』『教育者としてのショーペンハウアー』『バ
イロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』の4冊の「反時代的考察」が書かれます。1871年から1876年です。『音楽の精神か
らの悲劇の誕生』が書かれ、ワーグナー主義者によるおそらく最良のワーグナー賛美の書である『バイロイトにおけるリヒャルト・
ワーグナー』が書かれた時期です。
シアの密儀から音楽が発生し、悲劇が音楽から生まれたことに熱狂したときから始まります。その気分から、『信仰者であり著
述家であるダヴィッド・フリードリッヒ・シュトラウス』『人生にとっての歴史の効用と害』『教育者としてのショーペンハウアー』『バ
イロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』の4冊の「反時代的考察」が書かれます。1871年から1876年です。『音楽の精神か
らの悲劇の誕生』が書かれ、ワーグナー主義者によるおそらく最良のワーグナー賛美の書である『バイロイトにおけるリヒャルト・
ワーグナー』が書かれた時期です。
第二期になると、ニーチェは『人間的な、あまりに人間的な』『曙光』『喜ばしき学問』を書きます。
処女作から1876年まで、ニーチェは最高の意味で理想主義者であり、すべてを理想へと高めようとしました。第二期になると、
ニーチェはあらゆる理想主義に別れを告げます。彼は理想を茶化します。「理想を持ち出すのは、人生において虚弱だからだ。
人生においてなにごとも成し遂げられない人は、人生は無価値なもので、理想を追及しなければならないという」と、彼は考えま
した。そして、ニーチェは個々の理想を攻撃し、神的なものが自然のなかに示すものをあまりに人間的なもの、取るに足りないも
のとしました。ニーチェはヴォルテール主義者になり、『人間的な、あまりに人間的な』をヴォルテールに捧げました。ニーチェは
まったく合理主義者、主知主義者になりました。この時期は、1882年、1883年までつづきます。ついで、第三期にいたり、彼
は永劫回帰の理念を形成し、ツァラトゥストラを人間の理想とします。彼は讃歌のスタイルで、『ツァラトゥストラはこう語った』を書
きます。
ニーチェはあらゆる理想主義に別れを告げます。彼は理想を茶化します。「理想を持ち出すのは、人生において虚弱だからだ。
人生においてなにごとも成し遂げられない人は、人生は無価値なもので、理想を追及しなければならないという」と、彼は考えま
した。そして、ニーチェは個々の理想を攻撃し、神的なものが自然のなかに示すものをあまりに人間的なもの、取るに足りないも
のとしました。ニーチェはヴォルテール主義者になり、『人間的な、あまりに人間的な』をヴォルテールに捧げました。ニーチェは
まったく合理主義者、主知主義者になりました。この時期は、1882年、1883年までつづきます。ついで、第三期にいたり、彼
は永劫回帰の理念を形成し、ツァラトゥストラを人間の理想とします。彼は讃歌のスタイルで、『ツァラトゥストラはこう語った』を書
きます。
そして、彼はワーグナーについて、ふたたび書きます。それは、たいへん注目に値するものです。ニーチェの方法を知っている
と、その著は注目すべきものに見えます。『バイロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』は、リヒャルト・ワーグナーに熱狂した壮大
な讃歌です。第三期に、『ワーグナー事件』が書かれました。ワーグナーに反対していいうることすべてが、この本のなかに書か
れています。
と、その著は注目すべきものに見えます。『バイロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』は、リヒャルト・ワーグナーに熱狂した壮大
な讃歌です。第三期に、『ワーグナー事件』が書かれました。ワーグナーに反対していいうることすべてが、この本のなかに書か
れています。
ありきたりにいえば、「ニーチェは変ったのだ。ニーチェは「見解を変えたのだ」と、いうことです。しかし、ニーチェの原稿を知って
いる者は、そうはいいません。ニーチェは『バイロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』の2、3ページをワーグナーへの熱狂的な
讃歌として書いたとき、自分が書いたのと反対のことを同時に書いていました。そして、また、また讃歌を書き、また反対のこと
を書きました。『ワーグナー事件』は、すでに1876年に書かれていたのです。彼はそれをしまっておき、讃歌の部分だけを『バイ
ロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』として印刷したのです。彼は、昔書いたものを取り出し、鋭い文章をいくつか加えただけな
のです。
いる者は、そうはいいません。ニーチェは『バイロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』の2、3ページをワーグナーへの熱狂的な
讃歌として書いたとき、自分が書いたのと反対のことを同時に書いていました。そして、また、また讃歌を書き、また反対のこと
を書きました。『ワーグナー事件』は、すでに1876年に書かれていたのです。彼はそれをしまっておき、讃歌の部分だけを『バイ
ロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』として印刷したのです。彼は、昔書いたものを取り出し、鋭い文章をいくつか加えただけな
のです。
彼は第三期に、第一期に控えていた攻撃をなすという傾向がありました。彼が『バイロイトにおけるリヒャルト・ワーグナー』に載
せずにしまっておいた原稿が失われていたなら、『ワーグナー事件』は世に出なかったでしょう。
せずにしまっておいた原稿が失われていたなら、『ワーグナー事件』は世に出なかったでしょう。
この三つの時期を追っていくと、それらを一貫する性格があるのがわかります。彼のべつの面が示された最後の作品『偶像のた
そがれ、あるいは、いかにしてハンマーで哲学するか』にいたるまで、ニーチェの霊性の基本性格が見られます。ニーチェはほん
とうにいきいきと、イメージ豊かに書いてます。たとえば、彼はフランスの歴史家ジュール・ミシュレの性格を述べようとしました。
彼の性格描写は適切なもので、「熱中したときには、もろはだ脱ぎになる」と、書いています。これは、ミシュレのある面を見事に
とらえています。同様のことが、『偶像のたそがれ』のなかに、いきいきと述べられています。(P206-209)
そがれ、あるいは、いかにしてハンマーで哲学するか』にいたるまで、ニーチェの霊性の基本性格が見られます。ニーチェはほん
とうにいきいきと、イメージ豊かに書いてます。たとえば、彼はフランスの歴史家ジュール・ミシュレの性格を述べようとしました。
彼の性格描写は適切なもので、「熱中したときには、もろはだ脱ぎになる」と、書いています。これは、ミシュレのある面を見事に
とらえています。同様のことが、『偶像のたそがれ』のなかに、いきいきと述べられています。(P206-209)
魂を拷問にかける
「かつての秘儀参入者はどこにいるのか」という問いに戻りましょう。秘儀参入者はいない、といわれるかもしれません。逆説的
な言い方になりますが、もし今日、魂が霊的世界から17、8歳の身体に下り、今日の学校教育を受けないですんだなら、秘儀参
入者が現れることができます。古代の叡智を、今日の文明のなかで17、8歳まで育てられてきた身体のなかに出現させるのは
不可能なのです。世界のどこでも、不可能です。すくなくとも、文明のあるところでは不可能です。今日の学者の視野には入らな
いことを、考察しなければなりません。
な言い方になりますが、もし今日、魂が霊的世界から17、8歳の身体に下り、今日の学校教育を受けないですんだなら、秘儀参
入者が現れることができます。古代の叡智を、今日の文明のなかで17、8歳まで育てられてきた身体のなかに出現させるのは
不可能なのです。世界のどこでも、不可能です。すくなくとも、文明のあるところでは不可能です。今日の学者の視野には入らな
いことを、考察しなければなりません。
今日のように、6、7歳で読み書きを習わねばならないと、それは経済を発展させようとしている魂を拷問にかけていることになり
ます。『自伝』にも書きましたが、わたしが今日あるのは、12歳になるまで正しく書くことができなかったからです。今日のように
子どもに読み書きを教えると、その子の特性を殺すことになります。(P256-P257)
ます。『自伝』にも書きましたが、わたしが今日あるのは、12歳になるまで正しく書くことができなかったからです。今日のように
子どもに読み書きを教えると、その子の特性を殺すことになります。(P256-P257)