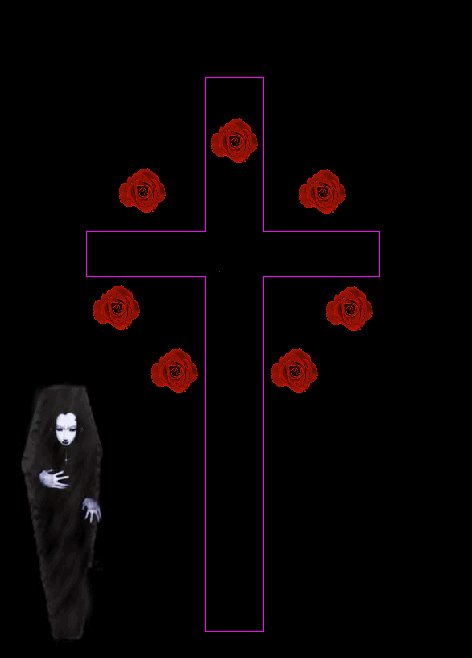���t�̋C�����q�ǂ��̐g�̂ɗ^����e��
�����������t�Ƃ��āA����҂Ƃ��Ďq�ǂ��̐��܂�Ă���ŏ���7�N�Ԃɗ^�����ۂ́A�q�ǂ��̌��s�A�ċz�A�����ɍ�p���y
�ڂ��܂����A���̍�p�́A�Ƃ��ɂ�40�A50���̌��N�ƕa�C�ƂȂ��Č���邱�Ƃ�����܂��B�ł�����A����҂��c���ɐڂ�
��Ƃ��̑ԓx�����̎q�̏����̍K�ƕs�K�A���N�ƕa�C�������錴���ɂȂ肤��̂ł��B
�ڂ��܂����A���̍�p�́A�Ƃ��ɂ�40�A50���̌��N�ƕa�C�ƂȂ��Č���邱�Ƃ�����܂��B�ł�����A����҂��c���ɐڂ�
��Ƃ��̑ԓx�����̎q�̏����̍K�ƕs�K�A���N�ƕa�C�������錴���ɂȂ肤��̂ł��B
���̐l���̐^�����A�悭�킫�܂��Ă��ĉ������B���̐^���́A�������ł̕����w��̐��ʂ�A���W�����ł̐A���̌`�ԂƂ܂�
���������悤�ɁA�悭�ώ@�ł��邱�ƂȂ̂ł��B�������A�l�͒ʏ킻�������ώ@�����悤�Ƃ��܂���B
���������悤�ɁA�悭�ώ@�ł��邱�ƂȂ̂ł��B�������A�l�͒ʏ킻�������ώ@�����悤�Ƃ��܂���B
���������A�w�Z�Ő搶�����k�̉��ɗ����Ă���Ƃ��܂��B���̐搶�̋C���́A���͓I�ŁA�{����ۂ��_�`���ł����B�܂�
�́A�����I�ŁA�������g�̕��ɂ����������A�����ɑ��Ă͕q���ł����Ă��A���Ԃ���g�����ނ������ȗJ�T���ł����B��
���͊O���痈���ۂ������ɋC�ɂȂ�A��ۂ����ۂւƂ����낪�ڂ��Ă����������ł����B�܂��͂��ׂĂ��Ȃ�䂫�ɂ܂����A
�O���痈���ۂɂ͂���قǂ����������邱�Ƃ̂Ȃ��S�t���ł����B
�́A�����I�ŁA�������g�̕��ɂ����������A�����ɑ��Ă͕q���ł����Ă��A���Ԃ���g�����ނ������ȗJ�T���ł����B��
���͊O���痈���ۂ������ɋC�ɂȂ�A��ۂ����ۂւƂ����낪�ڂ��Ă����������ł����B�܂��͂��ׂĂ��Ȃ�䂫�ɂ܂����A
�O���痈���ۂɂ͂���قǂ����������邱�Ƃ̂Ȃ��S�t���ł����B
�����ɂȂ邽�߂̗{���{�݂ŁA�������������̋C���ƈӎ��I�Ɍ����������ƂȂ��A�C����������Ԃɂ��Ă������Ƃ��܂��B����
�Ď��̐����ς��܂ł̎q�ǂ����A���������搶�̒_�`���ɂ����ɐG�ꑱ�����Ƃ��܂��B�搶���_�`�����ނ��o���ɂ��Ďq�ǂ�
�ɐڂ��Ă����Ƃ��܂��ƁA���̎q�̏z�n�A���I�ȃ��Y���͋�����ۂ������܂��B���߂̂����͈�ۂ��[�������Ă����܂�
�A���̈�ۂ��G��ƂȂ��Ďc��̂ł��B�����ĖG��͐������Ă����܂�����A�Ƃ��ɂ�40�A50�̍��̏z�n�ɐ搶��
�ނ��o���̒_�`���̉e��������Ă���̂ł��B�������͎q�ǂ����A�q�ǂ��̂Ƃ��̂��߂ɋ��炷�邾���łȂ��A�q�ǂ��̈ꐶ�̂�
�߂ɋ��炷��̂ł��B�����Ă���ɂ́A���̐��̈ꐶ����Ƃ��̂��߂ɂ����炷��̂ł��B
�Ď��̐����ς��܂ł̎q�ǂ����A���������搶�̒_�`���ɂ����ɐG�ꑱ�����Ƃ��܂��B�搶���_�`�����ނ��o���ɂ��Ďq�ǂ�
�ɐڂ��Ă����Ƃ��܂��ƁA���̎q�̏z�n�A���I�ȃ��Y���͋�����ۂ������܂��B���߂̂����͈�ۂ��[�������Ă����܂�
�A���̈�ۂ��G��ƂȂ��Ďc��̂ł��B�����ĖG��͐������Ă����܂�����A�Ƃ��ɂ�40�A50�̍��̏z�n�ɐ搶��
�ނ��o���̒_�`���̉e��������Ă���̂ł��B�������͎q�ǂ����A�q�ǂ��̂Ƃ��̂��߂ɋ��炷�邾���łȂ��A�q�ǂ��̈ꐶ�̂�
�߂ɋ��炷��̂ł��B�����Ă���ɂ́A���̐��̈ꐶ����Ƃ��̂��߂ɂ����炷��̂ł��B
�ʂ̗��������A�J�T���̐l�������̋C�����ނ��o���ɂ��āA�����{�����Ԓ��ɂ��̋C���a�����邱�Ƃ��Ȃ��A������
�d���Ŏq�ǂ��Ɍ����������Ƃ���Փ����Ƃ邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ��܂��B�����Ďq�ǂ��ƌ��������Ă��A�����̗J�T���ɏ]������
�܂ł����Ƃ��܂��B���̂悤�ȑԓx�ōl������A�������肵�Ă����Ƃ��܂��ƁA�{���A�搶���琶�k�֗���Ă����ׂ��M���A�t�ɐ�
�k����搶�̗���Ă����Ă��܂��܂��B���̌��ʁA���Ƃɍ��̔M�������Ă��܂��A���̉e�����q�ǂ������n�ɋy�сA�����n��
���ŖG��ƂȂ��đ��݂������܂��B�����Č�N�A���njn�ɂ��낢��ȏ�Q���A���t�̕a�C��������̂ł��B
�d���Ŏq�ǂ��Ɍ����������Ƃ���Փ����Ƃ邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ��܂��B�����Ďq�ǂ��ƌ��������Ă��A�����̗J�T���ɏ]������
�܂ł����Ƃ��܂��B���̂悤�ȑԓx�ōl������A�������肵�Ă����Ƃ��܂��ƁA�{���A�搶���琶�k�֗���Ă����ׂ��M���A�t�ɐ�
�k����搶�̗���Ă����Ă��܂��܂��B���̌��ʁA���Ƃɍ��̔M�������Ă��܂��A���̉e�����q�ǂ������n�ɋy�сA�����n��
���ŖG��ƂȂ��đ��݂������܂��B�����Č�N�A���njn�ɂ��낢��ȏ�Q���A���t�̕a�C��������̂ł��B
���ׂĂɖ��ڒ��ȔS�t���̐l���A���k�Ƃ̊Ԃɓ��ʂ̊W�������܂��B���t�Ɛ��k�Ƃ̊Ԃ��₽���Ƃ������́A���I�ɂ�
���낵�������I�ɂȂ�̂ł��B�ǂ��ɂ��艞����������ꂸ�A���t�Ɛ��k�Ƃ̊Ԃō��̌𗬂��s�m���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���k�͓��I�Ɏv�����芈�����邱�Ƃ��ł��܂���B���������S�t���̉e�������q�ǂ����A�ӔN�Ɏ���܂ŒH���Ă����܂��ƁA
�]�̏�Q�A�]�̕n���������Ƃ��ƂɂȂ��Č���Ă���̂��F�߂��܂��B
���낵�������I�ɂȂ�̂ł��B�ǂ��ɂ��艞����������ꂸ�A���t�Ɛ��k�Ƃ̊Ԃō��̌𗬂��s�m���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���k�͓��I�Ɏv�����芈�����邱�Ƃ��ł��܂���B���������S�t���̉e�������q�ǂ����A�ӔN�Ɏ���܂ŒH���Ă����܂��ƁA
�]�̏�Q�A�]�̕n���������Ƃ��ƂɂȂ��Č���Ă���̂��F�߂��܂��B
�������̐搶�̏ꍇ���l���Ă݂܂��傤�B���̐搶�́A�ǂ�Ȉ�ۂɂ����ӂ������܂��B�������A�����ɕʂ̕��ɒ��ӂ������
���܂��܂��B���̋C���̐搶�́A�����ɂ����k�����ɂ��A���ʂȑԓx�ŗՂ݂܂��B�搶����ۂ����ۂֈڂ�ς���Ă�����
�ŁA���k�͂ƂĂ����Ă����܂���B�q�ǂ������I�ɐ��������Ƃ��Ă����邽�߂ɂ́A�ЂƂ̈�ۂ����������ĎƂ߁A��
����������Ə�������K�v������̂ł��B���������������̋��t�̉��ŋ�������q�ǂ��́A��N�ɂȂ��āA�����͂Ɍ����A
�d���Ȑl���A�����̂���ԓx���������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
���܂��܂��B���̋C���̐搶�́A�����ɂ����k�����ɂ��A���ʂȑԓx�ŗՂ݂܂��B�搶����ۂ����ۂֈڂ�ς���Ă�����
�ŁA���k�͂ƂĂ����Ă����܂���B�q�ǂ������I�ɐ��������Ƃ��Ă����邽�߂ɂ́A�ЂƂ̈�ۂ����������ĎƂ߁A��
����������Ə�������K�v������̂ł��B���������������̋��t�̉��ŋ�������q�ǂ��́A��N�ɂȂ��āA�����͂Ɍ����A
�d���Ȑl���A�����̂���ԓx���������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
����ɂ͍��̂��܂₩�Ȃ܂Ȃ������K�v�Ȃ̂ł����A����������ŁA40�A50�ɂȂ����l�����Ă݂�ƁA���̐l���ǂ�ȋC��
�̐搶�Ɋw�̂����������Ă邱�Ƃ����ł��邭�炢�Ȃ̂ł��B
�̐搶�Ɋw�̂����������Ă邱�Ƃ����ł��邭�炢�Ȃ̂ł��B
�ȏ�̂��Ƃ����߂ɐ\���グ���̂́A�����@�ɖ𗧂ĂĂ������������Ǝv��������ł͂���܂���B�q�ǂ��̋���ɂ����āA����
��̎����̓�����������̎����ɗ��܂邱�Ƃ͂Ȃ��A�K�����炾�Ɉڂ��Ă����A�Ƃ������Ƃ��A�܂��w�E���Ă���������������ł��B
�q�ǂ��̂���������炷��Ƃ����̂́A���̐l�̑S���U�ɂ킽�邩�炾�̏�Ԃ����E���邱�Ƃ�����Ă��邱�ƂȂ̂ł��B(P88-
P91)
��̎����̓�����������̎����ɗ��܂邱�Ƃ͂Ȃ��A�K�����炾�Ɉڂ��Ă����A�Ƃ������Ƃ��A�܂��w�E���Ă���������������ł��B
�q�ǂ��̂���������炷��Ƃ����̂́A���̐l�̑S���U�ɂ킽�邩�炾�̏�Ԃ����E���邱�Ƃ�����Ă��邱�ƂȂ̂ł��B(P88-
P91)
����|�p
����|�p�͖{���A�l�Ԃ�{���ɔF��������łȂ��ƁA���H���邱�Ƃ��ł��܂���B�����Ė{���ɐl�Ԃ�F������ɂ́A�����l�@
���s�������ł͕s�\���Ȃ̂ł��B�l�Ԃ̖{�����g�̒m���ɂ���Ēm�邱�Ƃ͂ł��܂���B�l�Ԃ��u�m�낤�v�Ǝv���Ȃ�A���Ȃ�
�Ƃ�������x�܂ŁA������������g�̖{���̒��ɓ����Ă���n�����ɑ����āA�u�������Ȃ���v�Ȃ�܂���B�����������
�ӎu�s�ׂ�ʂ��Ċ����Ƃ�Ȃ���Ȃ�܂���B
���s�������ł͕s�\���Ȃ̂ł��B�l�Ԃ̖{�����g�̒m���ɂ���Ēm�邱�Ƃ͂ł��܂���B�l�Ԃ��u�m�낤�v�Ǝv���Ȃ�A���Ȃ�
�Ƃ�������x�܂ŁA������������g�̖{���̒��ɓ����Ă���n�����ɑ����āA�u�������Ȃ���v�Ȃ�܂���B�����������
�ӎu�s�ׂ�ʂ��Ċ����Ƃ�Ȃ���Ȃ�܂���B
�l�Ԃ̂��Ƃ������g�̎p���Ŋw�Ԍ���A���̒m���͋�����H�ɑ��Ă͗}���I�ȍ�p�����y�ڂ��܂���B�Ȃ��Ȃ炻�̂�
���Ȓm�������H�Ɉڂ����Ƃ���A����҂͋����@���A�����O���狳�����܂ꂽ���̂Ƃ��Ă�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������
���B����҂������ł��̂悤�ȋ����@�����グ���Ƃ��Ă��A���̓��e�͖{���I�ɂ͊O����^����ꂽ���̂Ȃ̂ł��B
���Ȓm�������H�Ɉڂ����Ƃ���A����҂͋����@���A�����O���狳�����܂ꂽ���̂Ƃ��Ă�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������
���B����҂������ł��̂悤�ȋ����@�����グ���Ƃ��Ă��A���̓��e�͖{���I�ɂ͊O����^����ꂽ���̂Ȃ̂ł��B
����w�̊�b�ƂȂ�l�ԔF���́A��������l�������̒��ł�����܂����������Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B��������������
�ċz���A���������t���z���Ă���Ƃ��A�����̐g�̂����N�ł���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɁA�l�Ԃɂ��Ă̎������̔F��
���A���ꂪ�������̒��Ő�������Ă��Ȃ���A�����̂��̂Ƃ��đ̌����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B
�ċz���A���������t���z���Ă���Ƃ��A�����̐g�̂����N�ł���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɁA�l�Ԃɂ��Ă̎������̔F��
���A���ꂪ�������̒��Ő�������Ă��Ȃ���A�����̂��̂Ƃ��đ̌����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B
�킽������������҂Ƃ��āA���Ƃ���Ƃ����傫�ȉۑ��������Ȃ�A�������̐l�ԔF�������Ƃ̒��ɂ܂œ��R�̂悤�ɗ�
��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ă��̓��R�̍s�ׂ̒��ɂ́u���v���\������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B��������A������
�g�Ȑl�ԔF���ȂǑ��݂���]�n�͂���܂��A�u��������Ύq�ǂ��͂����v�����낤�B�����炱�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƊO
�����炠�ꂱ��v�������肷��]�n������܂���B�����ɐ����ē������̂́A�����Œ��ڑ̌����邱�Ƃ̂ł������t�̐l�ԔF��
�����ł��B���̔F���͋��t�́u���ȔF���v�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��̂ł��B�����Ă��̔F����ʂ��Ă����A����ɂ�����q�ǂ���
�̓����������K�R�I�Ɉ��Ƃ��Ă̐��������悤�ɂȂ�̂ł��B�����Ă��̂��Ƃ͎q�ǂ���{���ɑ̌����邱�Ƃł�����̂ł��B
�Ⴊ�F�ʂ��������悤�ɁA���������Ƃ����l�ԔF���́A�q�ǂ��̖{����̌�����̂ł��B
��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ă��̓��R�̍s�ׂ̒��ɂ́u���v���\������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B��������A������
�g�Ȑl�ԔF���ȂǑ��݂���]�n�͂���܂��A�u��������Ύq�ǂ��͂����v�����낤�B�����炱�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƊO
�����炠�ꂱ��v�������肷��]�n������܂���B�����ɐ����ē������̂́A�����Œ��ڑ̌����邱�Ƃ̂ł������t�̐l�ԔF��
�����ł��B���̔F���͋��t�́u���ȔF���v�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��̂ł��B�����Ă��̔F����ʂ��Ă����A����ɂ�����q�ǂ���
�̓����������K�R�I�Ɉ��Ƃ��Ă̐��������悤�ɂȂ�̂ł��B�����Ă��̂��Ƃ͎q�ǂ���{���ɑ̌����邱�Ƃł�����̂ł��B
�Ⴊ�F�ʂ��������悤�ɁA���������Ƃ����l�ԔF���́A�q�ǂ��̖{����̌�����̂ł��B
���R�F���͗��_�ł����Ă����܂��܂��A�l�ԔF�������_�ɗ��܂�ƁA���S�Ȋ��̎�����ɂƂ��āA����͂܂�Ől��
�̍��i������̌��������Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�l�ԔF���ɂ����闝�_�Ǝ��H�̑����������_���Ă��A���ɂ��Ȃ�܂�
��B�Ȃ��Ȃ琶���̒��ɖ{���I�ȍ�p���y�ڂ����Ƃ̂ł��Ȃ��l�ԔF���́A���̒��ʼne�̂悤�ɕ��V����\�ۓ��e�̋�������
�W�����ł͂����Ă��A�l�Ԃɐ[���ւ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł��B���������̋t�ɁA�{���̐l�ԔF���̌������ɂ��鐶���s
�ׂ��A�s�m���ȑ��ǂ�ňÈł̒���͍��������Ȃ̂ł��B
�̍��i������̌��������Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�l�ԔF���ɂ����闝�_�Ǝ��H�̑����������_���Ă��A���ɂ��Ȃ�܂�
��B�Ȃ��Ȃ琶���̒��ɖ{���I�ȍ�p���y�ڂ����Ƃ̂ł��Ȃ��l�ԔF���́A���̒��ʼne�̂悤�ɕ��V����\�ۓ��e�̋�������
�W�����ł͂����Ă��A�l�Ԃɐ[���ւ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł��B���������̋t�ɁA�{���̐l�ԔF���̌������ɂ��鐶���s
�ׂ��A�s�m���ȑ��ǂ�ňÈł̒���͍��������Ȃ̂ł��B
�ȏ�ɏq�ׂ����Ƃ�����҂́u�S�\���v�ɂȂ�A���ꂾ���Ŏq�ǂ������̑O�Ő��������Ƃ������t�̎p���������Ƃ��ł���ł�
�傤�B�����Đ���������q�ǂ��ɑ��āA�����Ŏ��������炷��悤�ɁA�ƗD�����������Ƃ��ł���ł��傤�B
�傤�B�����Đ���������q�ǂ��ɑ��āA�����Ŏ��������炷��悤�ɁA�ƗD�����������Ƃ��ł���ł��傤�B
�����A�u����҂Ƃ��Ă̐������S�\���v���������ׂĂ̋�����H�ɂ�����{�������Ȃ̂ł��B
���̂悤�ȐS�\���ɂ���āA�����́u�S�l�v�̖G��ł���q�ǂ��̐����ߒ��������Ă��܂��B
���ƂȂ͋@�B�I�ȘJ���̒��ł����������������ƂȂ��A���̑S�l��J���̒��ɐ��������Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�ǂ�Ȏq�ǂ���
�{�����A�l�ԑS�̖̂{����\�����Ƃ̂ł���悤�ȘJ���ւ̏������s�������Ǝv���Ă��܂��B�ǂ�Ȏq�ǂ����A�������邱�Ƃ��l
�Ԃ̖{���Ɋ�Â��Ă��邩�炱���A�����������̂ł��B���ƂȂ̏ꍇ�A���������Ԃ�����̌��߂�ꂽ��Ƃ����߂܂��B�q�ǂ�
�̏ꍇ�A��������l�Ԗ{���͋��t�ɐ�����������āA�����̎Љ�J���̖G��ƂȂ肤��悤�Ȋ��������߂܂��B(P94)
�{�����A�l�ԑS�̖̂{����\�����Ƃ̂ł���悤�ȘJ���ւ̏������s�������Ǝv���Ă��܂��B�ǂ�Ȏq�ǂ����A�������邱�Ƃ��l
�Ԃ̖{���Ɋ�Â��Ă��邩�炱���A�����������̂ł��B���ƂȂ̏ꍇ�A���������Ԃ�����̌��߂�ꂽ��Ƃ����߂܂��B�q�ǂ�
�̏ꍇ�A��������l�Ԗ{���͋��t�ɐ�����������āA�����̎Љ�J���̖G��ƂȂ肤��悤�Ȋ��������߂܂��B(P94)
����Ɠ����T
����҂ɂƂ��Ă̍ō��̉ۑ�́A�����Ɉς˂�ꂽ��҂̓����I�Ȑ����ԓx����Ă邽�߂ɉ������Ă������邩�A�Ƃ�������
�ł��B�����������w�Z�i���E���w�Z�j�̋���ɂ��������l�ɂƂ��āA���̉ۑ�͑�ύ���Ȃ��̂��ƌ����܂��B���̗��R�̂Ђ�
�́A��������͂��ׂĂ̎��Ƃ̒��ɐZ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B���̎��Ƃ���藣���ꂽ�u�����̎��ԁv����
����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̎��ԓ��ɒB�����ꂤ�鎖���́A������g�ɂ��������ŁA���̂ǂ�Ȏ��ƂɊr�ׂĂ��A�����Ɩ��ɗ���
�܂���B��������͋���s�ׂ��̂��̂̒��ɂ���̂�����ł��B���ہA�ǂ�ȏꍇ�ɂ����_�o�ɍ��グ��ꂽ�u�������_��
�ے��v�́A���Ƃ����̎��Ԃɂǂ�قLj�ې[���b���Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă��A���ƂɂȂ��Ă��̈Ӑ}�������ʂ������邱�Ƃ͂ł���
���ł��傤�B�����ЂƂʂ̍���́A���w�Z�ɓ��w�����q�ǂ������łɊ�{�I�ȓ����K��������܂ł̐����̒��ō��グ�Ă�
��A�Ƃ��������ɂ���܂��B
�ł��B�����������w�Z�i���E���w�Z�j�̋���ɂ��������l�ɂƂ��āA���̉ۑ�͑�ύ���Ȃ��̂��ƌ����܂��B���̗��R�̂Ђ�
�́A��������͂��ׂĂ̎��Ƃ̒��ɐZ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B���̎��Ƃ���藣���ꂽ�u�����̎��ԁv����
����ꂽ�Ƃ��Ă��A���̎��ԓ��ɒB�����ꂤ�鎖���́A������g�ɂ��������ŁA���̂ǂ�Ȏ��ƂɊr�ׂĂ��A�����Ɩ��ɗ���
�܂���B��������͋���s�ׂ��̂��̂̒��ɂ���̂�����ł��B���ہA�ǂ�ȏꍇ�ɂ����_�o�ɍ��グ��ꂽ�u�������_��
�ے��v�́A���Ƃ����̎��Ԃɂǂ�قLj�ې[���b���Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă��A���ƂɂȂ��Ă��̈Ӑ}�������ʂ������邱�Ƃ͂ł���
���ł��傤�B�����ЂƂʂ̍���́A���w�Z�ɓ��w�����q�ǂ������łɊ�{�I�ȓ����K��������܂ł̐����̒��ō��グ�Ă�
��A�Ƃ��������ɂ���܂��B
�q�ǂ��́A7�̍��̎��̐����ς�鎞���܂ł́A���S�Ɋ��ƈ�ɂȂ��Đ����Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁA�q�ǂ��͑S�̂���
�o�ł���A�ƌ����Ă��������炢�ł��B�Ⴊ����F�ʂƈ�ɂȂ��ē����悤�ɁA�q�ǂ��͂��̂��ׂĂ����̐����\���ƈ��
�Ȃ��Đ����Ă���̂ł��B���e�A��e�̈ꋓ����������ɉ������d���Ŏq�ǂ����Ȃ�͂Ɍ`������܂��B�[�����炱��
�����܂łɁA�]�g�D���l�Ԃ̓��Ȃ�͂ɂ���Č`������܂��B�����Ă��̔]����g�̂̂��ׂĂ̑g�D�����āA�����̑g�D
�ɓ���̌`�Ԃ�^���铭�����y�Ԃ̂ł��B���̍ہA�]�̒��ɂ́A�����Ȏd���Ŋ��ɓK�����A�g�D���`������Ă�����
���B�q�ǂ���������K���ł���̂͂܂��������̂��Ƃ̌��ʂȂ̂ł��B
�o�ł���A�ƌ����Ă��������炢�ł��B�Ⴊ����F�ʂƈ�ɂȂ��ē����悤�ɁA�q�ǂ��͂��̂��ׂĂ����̐����\���ƈ��
�Ȃ��Đ����Ă���̂ł��B���e�A��e�̈ꋓ����������ɉ������d���Ŏq�ǂ����Ȃ�͂Ɍ`������܂��B�[�����炱��
�����܂łɁA�]�g�D���l�Ԃ̓��Ȃ�͂ɂ���Č`������܂��B�����Ă��̔]����g�̂̂��ׂĂ̑g�D�����āA�����̑g�D
�ɓ���̌`�Ԃ�^���铭�����y�Ԃ̂ł��B���̍ہA�]�̒��ɂ́A�����Ȏd���Ŋ��ɓK�����A�g�D���`������Ă�����
���B�q�ǂ���������K���ł���̂͂܂��������̂��Ƃ̌��ʂȂ̂ł��B
����ǂ����̂�����́A���̊O���̕����������q�ǂ��̖{���ɍ�p���A���̓����ɍ���������̂ł͂���܂���B�O���̕�
���ƂƂ��ɁA���͂̐l�Ԃ̍��̓��e�A�������e����p���y�ڂ��̂ł��B����A�q�ǂ��̑O�ł����ɓ{���\�����e�́A�q�ǂ���
�ł������ȑg�D�\���̒��ɂ܂ŁA�{��ւ̌X��������悤�Ƃ��铭����g�ݍ��ނ̂ł��B�����Ђǂ����ǂ��ǂ��Ă����
�e�͎q�ǂ��̐g�̑g�D�̒��ɂ܂ł��̓������y�ڂ��āA�q�ǂ��̍����Ђǂ����ǂ��ǂ������̂ɂ��܂��B
���ƂƂ��ɁA���͂̐l�Ԃ̍��̓��e�A�������e����p���y�ڂ��̂ł��B����A�q�ǂ��̑O�ł����ɓ{���\�����e�́A�q�ǂ���
�ł������ȑg�D�\���̒��ɂ܂ŁA�{��ւ̌X��������悤�Ƃ��铭����g�ݍ��ނ̂ł��B�����Ђǂ����ǂ��ǂ��Ă����
�e�͎q�ǂ��̐g�̑g�D�̒��ɂ܂ł��̓������y�ڂ��āA�q�ǂ��̍����Ђǂ����ǂ��ǂ������̂ɂ��܂��B
���̐����ς�鍠�܂łɂ́A�q�ǂ��̐g�̑g�D�̒��ɑg�ݍ��܂ꂽ����̓����I�X�����q�ǂ��̍�������Â��Ă���̂�
���B
���B
���̏�Ԃ̉��ŁA�܂蓹���I�ɌX���Â���ꂽ�g�̑g�D���������q�ǂ��̋���������w�Z�̐搶�͈�����̂ł��B����
��������ł��Ȃ��搶�́A�q�ǂ������ӎ��ɋ��ۂ���ł��낤�悤�ȓ����Փ������q�ǂ��ɉ������悤�Ƃ��܂��B�������
����邱�Ƃɂ��炾����R���邩��q�ǂ��͋��ۂ���̂ł��B
��������ł��Ȃ��搶�́A�q�ǂ������ӎ��ɋ��ۂ���ł��낤�悤�ȓ����Փ������q�ǂ��ɉ������悤�Ƃ��܂��B�������
����邱�Ƃɂ��炾����R���邩��q�ǂ��͋��ۂ���̂ł��B
��������������ɂƂ��Ė{���I�Ȃ̂́A���w�Z�ɓ��w����q�ǂ�������܂ł̊��͕�ɂ���Ă��łɊ�{�I�Ȑ����ԓx��g
�ɂ��Ă��邱�ƁA�����Ă��̊�{�I�Ȑ����ԓx�����ꂩ��̊w�Z���̒��ŕω��ł��邱�ƁA���̂��Ƃ�����҂��悭�킫�܂�
�Ă��邱�ƂȂ̂ł��B�{��₷�����̒��ň�����q�́A���̊���ʂ��āA�g�̑g�D���琬���Ă��܂����B���̂��Ƃɒ��ӂ���
���Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��Ƃ��l���ɓ���Ȃ���Ȃ�܂���B�����������ω������邱�Ƃ͂ł���̂ł��B���̂��Ƃ���
���ł���A���̐����ς�肩��v�t���܂ł̑��E���N���ɁA�K�v�ɉ����āA�K�ȁA�v���[���A�f���Ƃ����ԓx�ŁA�q�ǂ�
�̍����x����p�ӂ����̂ǂ��Ă������܂��B�s���ȁA���т������ɗR������q�ǂ��̐g�̑g�D��㵒p�S�Ə���������
�Ɋ����鍂�M�ȋC��������Ă邱�ƂŁA���l�ɕK�v�Ȏx����^���Ă������܂��B���̂悤�ɐl�Ԃ̖{����{���ɔF�����邱��
���A��������ɂƂ��Ă���{�I�ɕK�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B
�ɂ��Ă��邱�ƁA�����Ă��̊�{�I�Ȑ����ԓx�����ꂩ��̊w�Z���̒��ŕω��ł��邱�ƁA���̂��Ƃ�����҂��悭�킫�܂�
�Ă��邱�ƂȂ̂ł��B�{��₷�����̒��ň�����q�́A���̊���ʂ��āA�g�̑g�D���琬���Ă��܂����B���̂��Ƃɒ��ӂ���
���Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��Ƃ��l���ɓ���Ȃ���Ȃ�܂���B�����������ω������邱�Ƃ͂ł���̂ł��B���̂��Ƃ���
���ł���A���̐����ς�肩��v�t���܂ł̑��E���N���ɁA�K�v�ɉ����āA�K�ȁA�v���[���A�f���Ƃ����ԓx�ŁA�q�ǂ�
�̍����x����p�ӂ����̂ǂ��Ă������܂��B�s���ȁA���т������ɗR������q�ǂ��̐g�̑g�D��㵒p�S�Ə���������
�Ɋ����鍂�M�ȋC��������Ă邱�ƂŁA���l�ɕK�v�Ȏx����^���Ă������܂��B���̂悤�ɐl�Ԃ̖{����{���ɔF�����邱��
���A��������ɂƂ��Ă���{�I�ɕK�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B
����҂͎��̐����ς��Ǝv�t���Ƃ̊ԂɎq�ǂ��̖{������ʂɂǂ��������B�𐋂��邩�A���̍ۉ����v������邩���悭��
�����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
�����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
������̊�{�ԓx��ω������A�������Ǝv���邱�Ƃ�L�����Ƃ��ł���悤�ɂ���ɂ́A������ɂ����铹���I�ȋ����A��
���ɂ܂ʼne�����y�Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ċ�����ɓ��������邱�Ƃ��ł���̂́A���ۓI�ȋK�͂◝�O�ł͂���܂�
��B�u�`�ہv�Ȃ̂ł��B�������͎��ƒ��A�q�ǂ��̍��Ɍ����Ĉ̑�Ȑl�Ԃ̐�������s�����`�ہi�C���[�W�j�Ƃ��Ē���@��
����邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȍ`�ہi�C���[�W�j�������I�ȋ����Ɣ����ɓ���������̂ł��B�����ɂ��Ă̂��̂悤�Ȋ���
���f�����̐����ς��Ǝv�t���̊ԂɈ琬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
���ɂ܂ʼne�����y�Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ċ�����ɓ��������邱�Ƃ��ł���̂́A���ۓI�ȋK�͂◝�O�ł͂���܂�
��B�u�`�ہv�Ȃ̂ł��B�������͎��ƒ��A�q�ǂ��̍��Ɍ����Ĉ̑�Ȑl�Ԃ̐�������s�����`�ہi�C���[�W�j�Ƃ��Ē���@��
����邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȍ`�ہi�C���[�W�j�������I�ȋ����Ɣ����ɓ���������̂ł��B�����ɂ��Ă̂��̂悤�Ȋ���
���f�����̐����ς��Ǝv�t���̊ԂɈ琬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
���������ς��܂ł̎q�ǂ��͋A�˂���ԓx�Ŋ��̐����\���ږ͕킷��̂ł����A���̐����ς��Ǝv�t���Ƃ̊Ԃ�
�́A����҂����Ђ������Č�錾�t���A�˂���ԓx�Ŏe��܂��B�������̑��E���N���ɁA����҂̂��̂�����Ȃ錠�Ђ�
�A�˓I�ɐڂ��A�����ʂ��Ď����𐬒������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ȃ�A���̌�̐l���ɂ����ē����I�Ȏ��R�ւ̈ӎ���ڊo
�߂����邱�Ƃ͂ł��܂���B����҂̌��Ђ̕K�v���ɂ��Ă͂��ׂĂ̋���Ɍ����邱�Ƃł����A�Ƃ�킯����͓��������
�Ƃ��ĕK�v�Ȃ̂ł��B���h����搶�̂��ŁA��������Ȃ���A�q�ǂ��͉����P���A���������̂����w�Ԃ̂ł��B�搶�͐�
�E�����̑�\�҂ł��B����������q�ǂ��͂܂��M���ł��邨�ƂȂ�ʂ��āA���E��m��悤�ɂȂ�̂ł��B
�́A����҂����Ђ������Č�錾�t���A�˂���ԓx�Ŏe��܂��B�������̑��E���N���ɁA����҂̂��̂�����Ȃ錠�Ђ�
�A�˓I�ɐڂ��A�����ʂ��Ď����𐬒������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ȃ�A���̌�̐l���ɂ����ē����I�Ȏ��R�ւ̈ӎ���ڊo
�߂����邱�Ƃ͂ł��܂���B����҂̌��Ђ̕K�v���ɂ��Ă͂��ׂĂ̋���Ɍ����邱�Ƃł����A�Ƃ�킯����͓��������
�Ƃ��ĕK�v�Ȃ̂ł��B���h����搶�̂��ŁA��������Ȃ���A�q�ǂ��͉����P���A���������̂����w�Ԃ̂ł��B�搶�͐�
�E�����̑�\�҂ł��B����������q�ǂ��͂܂��M���ł��邨�ƂȂ�ʂ��āA���E��m��悤�ɂȂ�̂ł��B
���̂悤�ɂ��Đ��E��m�邱�Ƃ̒��ɁA�ǂ�قǏd�v�ȋ���Փ������߂��Ă��邩��m�邽�߂ɂ́A���E���N���̎O���̈�
���߂����A�ق�9����10�ɂ����Ă̎q�ǂ��̂��Ƃ��A�{���ɂ悭�F�����悤�Ƃ��邱�Ƃ���ł��B�l���̂��̎��_�ŁA�ł�
�d�v�ȓ]�����̂ЂƂ��q�ǂ��͌}���܂��B�q�ǂ��͔��Ζ��ӎ��ɁA�����ꏭ�Ȃ���Â�����̓������ŁA����{���I�ɏd�v
�ȑ̌�����萋����̂ł��B���̂Ƃ��q�ǂ��ɂ��ƂȂ������������������Ƃ́A�q�ǂ��̂��̌�̐����S�̂��v���قǂ̉e��
���y�ڂ��܂��B���̎����̎q�ǂ������Ɏ�������̉c�݂̒��ő̌����鎖�����A�������ӎ��I�ȕ\���Ō��Ƃ���A���̂悤
�Ɍ���Ȃ���Ȃ�܂���B�q�ǂ��̍��̒��ɖ₢������Ă���̂ł��B�u�搶�͎������A���h�����߁A�M�������߂ĎƂ�
�Ă��邻�̗͂���̂ǂ����瓾�Ă���̂��v�B�������͂��̂悤�ɖ₤�q�ǂ��̖��ӎ��̍��̐[�݂Ɍ������āA����҂Ƃ��āA��
���̌��Ђ����E�����̒��ɂ�������ƍ������낵�Ă��邩�炱���������̂��A�Ǝ��ł��Ȃ���Ȃ�܂���B�{���̐l�ԔF��
�������Ƃ��ł���A���̎����̎q�ǂ��������炩�̌��t���A����ǂ��납�Ƃ��ɂ͂�������̌��t�����̂��Ƃ̂��߂ɕK�v�Ƃ�
�Ă���A�Ƃ������ƂɋC�Â��͂��ł��B��������I�ȑ̌������̎����ɂ͕K�v�Ȃ̂ł��B�����ĉ�������I�Ȃ̂��������Ă���
��̂́A�q�ǂ����g�̖{�������ł��B�����Ďq�ǂ��̓����I�ȗ́A�����I�Ȋm�����A�����ԓx�̂��߂ɁA�܂��ɂ������������ɂ�
���A�����\����قǂɏd�v�Ȏ���������҂͍s�����Ƃ��ł���̂ł��B
���߂����A�ق�9����10�ɂ����Ă̎q�ǂ��̂��Ƃ��A�{���ɂ悭�F�����悤�Ƃ��邱�Ƃ���ł��B�l���̂��̎��_�ŁA�ł�
�d�v�ȓ]�����̂ЂƂ��q�ǂ��͌}���܂��B�q�ǂ��͔��Ζ��ӎ��ɁA�����ꏭ�Ȃ���Â�����̓������ŁA����{���I�ɏd�v
�ȑ̌�����萋����̂ł��B���̂Ƃ��q�ǂ��ɂ��ƂȂ������������������Ƃ́A�q�ǂ��̂��̌�̐����S�̂��v���قǂ̉e��
���y�ڂ��܂��B���̎����̎q�ǂ������Ɏ�������̉c�݂̒��ő̌����鎖�����A�������ӎ��I�ȕ\���Ō��Ƃ���A���̂悤
�Ɍ���Ȃ���Ȃ�܂���B�q�ǂ��̍��̒��ɖ₢������Ă���̂ł��B�u�搶�͎������A���h�����߁A�M�������߂ĎƂ�
�Ă��邻�̗͂���̂ǂ����瓾�Ă���̂��v�B�������͂��̂悤�ɖ₤�q�ǂ��̖��ӎ��̍��̐[�݂Ɍ������āA����҂Ƃ��āA��
���̌��Ђ����E�����̒��ɂ�������ƍ������낵�Ă��邩�炱���������̂��A�Ǝ��ł��Ȃ���Ȃ�܂���B�{���̐l�ԔF��
�������Ƃ��ł���A���̎����̎q�ǂ��������炩�̌��t���A����ǂ��납�Ƃ��ɂ͂�������̌��t�����̂��Ƃ̂��߂ɕK�v�Ƃ�
�Ă���A�Ƃ������ƂɋC�Â��͂��ł��B��������I�ȑ̌������̎����ɂ͕K�v�Ȃ̂ł��B�����ĉ�������I�Ȃ̂��������Ă���
��̂́A�q�ǂ����g�̖{�������ł��B�����Ďq�ǂ��̓����I�ȗ́A�����I�Ȋm�����A�����ԓx�̂��߂ɁA�܂��ɂ������������ɂ�
���A�����\����قǂɏd�v�Ȏ���������҂͍s�����Ƃ��ł���̂ł��B
�v�t���܂łɓ����I�Ȋ���f���������d���ň琬�����Ȃ�A���̑�O�E���N���ɂȂ��āA���̔��f�����R�Ȉӎu�̒���
���������ł��傤�B�����w�Z�𑲋Ƃ�����҂����͍����w�Z����̍��̍�p���p���A�����̒��̓����Փ��𑼂̐l
�����Ƃ̎Љ�I�ȋ��������̒��ŁA�����̑��݂̓������甭�W�����悤�Ɗ肢�Ȃ���A��������悤�ɂȂ�ł��傤�B�����Ă���
�܂łɐ������琬���ꂽ�����I�Ȋ���f�̒��ʼn萶���Ă���ӎu���A�����I�ɗ͋������݂ƂȂ��čs���̒��Ɍ���Ă����
���傤�B(P100-P105)
���������ł��傤�B�����w�Z�𑲋Ƃ�����҂����͍����w�Z����̍��̍�p���p���A�����̒��̓����Փ��𑼂̐l
�����Ƃ̎Љ�I�ȋ��������̒��ŁA�����̑��݂̓������甭�W�����悤�Ɗ肢�Ȃ���A��������悤�ɂȂ�ł��傤�B�����Ă���
�܂łɐ������琬���ꂽ�����I�Ȋ���f�̒��ʼn萶���Ă���ӎu���A�����I�ɗ͋������݂ƂȂ��čs���̒��Ɍ���Ă����
���傤�B(P100-P105)
����Ɠ����U
��I�F���̑��i�K�ɗ��ƁA�����̏u�Ԃ����ɐ��E�Ɗւ�荇���Ă���̂ł͂Ȃ��A���܂�Ă���o�����Ă�������܂ł�
�l���̂ǂ̏u�Ԃɂ������߂邱�Ƃ��ł���A�Ǝv����悤�ɂȂ�܂��B
�l���̂ǂ̏u�Ԃɂ������߂邱�Ƃ��ł���A�Ǝv����悤�ɂȂ�܂��B
18�A15�̍��ɗ����߂��āA���̓����̑̌����A�e�̂悤�Ȏv���o�Ƃ��Ă����łȂ��A�����Ă����Ƃ��Ɠ����؎����A��������
��͂ŁA�Ǒ̌��ł���悤�ɂȂ�̂ł��B���̂Ƃ��̎������́A�ӂ�����15�A12�ɂȂ��̂ł��B���������A������̓���
�ŁA���̗�I�ȕϗe��̌�����Ƃ��A���̂��炾�ł���u�G�[�e���́v�Ƃ��������Ȃ��炾�ɏo��܂��B�G�[�e���̂Ƃ́A��
�ԓ��̂��炾�Ƃ͈Ⴂ�A�̏d�̂Ȃ��A���Ԃ̂��炾�̂��Ƃł��B
��͂ŁA�Ǒ̌��ł���悤�ɂȂ�̂ł��B���̂Ƃ��̎������́A�ӂ�����15�A12�ɂȂ��̂ł��B���������A������̓���
�ŁA���̗�I�ȕϗe��̌�����Ƃ��A���̂��炾�ł���u�G�[�e���́v�Ƃ��������Ȃ��炾�ɏo��܂��B�G�[�e���̂Ƃ́A��
�ԓ��̂��炾�Ƃ͈Ⴂ�A�̏d�̂Ȃ��A���Ԃ̂��炾�̂��Ƃł��B
���̂Ƃ��̎������́A��C�ɁA�G�[�e���̂ɍ���Â������ԓ��̏o�����̂��ׂĂ�ʊς��܂��B�����Ă�����\�ɂ��Ă����
���G�[�e���̂Ȃ̂ł��B���̐����Ȃ��炾�̒��́A��Ԃ̂��炾�i���́j�Ɠ����悤�ɁA�����������̒��ɐ����Ă��邩�炾�Ȃ�
�ł��B
���G�[�e���̂Ȃ̂ł��B���̐����Ȃ��炾�̒��́A��Ԃ̂��炾�i���́j�Ɠ����悤�ɁA�����������̒��ɐ����Ă��邩�炾�Ȃ�
�ł��B
���Ƃ��A�������������̓��ɂɔY�܂����Ƃ��A���̓��ɂ������̂ɁA�֔���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B����
����Ɏ��Â���̂ł͂Ȃ��A���Ƃ������ꂽ�����ɂ���K�v������̂ł��B���̂悤�ɁA�������̒S���Ă���u��Ԃ�
���炾�v�̒��ł́A�ǂ̕��������݂Ɋ֘A�������Ă��܂����A���������́u�G�[�e�������ԑ́v�ɂ����Ă��A�������Ƃ�������̂�
���B�G�[�e���̂́A���ɗc�����Ɋ����ȓ����������Ă��܂����A�������ꐶ�̊ԓ��������A���Ƃ��Ύ��̂悤�ȓ����������Ă�
��܂��B
����Ɏ��Â���̂ł͂Ȃ��A���Ƃ������ꂽ�����ɂ���K�v������̂ł��B���̂悤�ɁA�������̒S���Ă���u��Ԃ�
���炾�v�̒��ł́A�ǂ̕��������݂Ɋ֘A�������Ă��܂����A���������́u�G�[�e�������ԑ́v�ɂ����Ă��A�������Ƃ�������̂�
���B�G�[�e���̂́A���ɗc�����Ɋ����ȓ����������Ă��܂����A�������ꐶ�̊ԓ��������A���Ƃ��Ύ��̂悤�ȓ����������Ă�
��܂��B
35�̐l���A�V�����l���̓]�@���}�����Ƃ��A��̑O�̏��悭�݂̂���ŁA�K�v�ȍs�����Ƃ邱�Ƃ��ł����ꍇ�A���A����
���������f���A�����s���ł����̂́A����12�������Ƃ��A�܂���8�������Ƃ��̐搶����w���Ƃ̂��������A�Ǝv���邱
�Ƃ�����܂��B35�̂��̐l�́A8��12�̂Ƃ��ɐ搶������������A�ӂ����э���тƂȂ��ċP���̂������܂��B�搶
��8��10�̃G�[�e���̂ɗ^���Ă��ꂽ���̂��A----���傤�Ǔ����痣�ꂽ�Ƃ���ɂ���튯�����ɂ���������������悤��-
---�������ꂽ��N�ɗ��h�ȓ��������Ă����̂ł��B6�܂���12�̂Ƃ��ɑ̌��������Ƃ́A35�ΈȌ�ɂȂ��Ă������A����
�Ċ�т̋C����ӂ������C�������ыN�����̂ł��B�ŔӔN�̐l�̐S�g�̏�Ԃ́A��ԑ́i���́j�̈���튯�����ꂽ�Ƃ����
����ʂ̊튯�Ɉˑ����Ă���悤�ɁA���ėc�����ɐ搶�����ԑ́i�G�[�e���́j�ɗ^�����̌��Ɉˑ����Ă���̂ł��B(P106
-P108)
���������f���A�����s���ł����̂́A����12�������Ƃ��A�܂���8�������Ƃ��̐搶����w���Ƃ̂��������A�Ǝv���邱
�Ƃ�����܂��B35�̂��̐l�́A8��12�̂Ƃ��ɐ搶������������A�ӂ����э���тƂȂ��ċP���̂������܂��B�搶
��8��10�̃G�[�e���̂ɗ^���Ă��ꂽ���̂��A----���傤�Ǔ����痣�ꂽ�Ƃ���ɂ���튯�����ɂ���������������悤��-
---�������ꂽ��N�ɗ��h�ȓ��������Ă����̂ł��B6�܂���12�̂Ƃ��ɑ̌��������Ƃ́A35�ΈȌ�ɂȂ��Ă������A����
�Ċ�т̋C����ӂ������C�������ыN�����̂ł��B�ŔӔN�̐l�̐S�g�̏�Ԃ́A��ԑ́i���́j�̈���튯�����ꂽ�Ƃ����
����ʂ̊튯�Ɉˑ����Ă���悤�ɁA���ėc�����ɐ搶�����ԑ́i�G�[�e���́j�ɗ^�����̌��Ɉˑ����Ă���̂ł��B(P106
-P108)
�i�����j
�q�ǂ���9��10�̊Ԃ̎��_�ɒB�����Ƃ��A���Ɏq�ǂ��̑n���͂��h������C���[�W�����グ�邱�Ƃ���ł��B����������
�N������悤�Ȑ������̃C���[�W���ł��B�q�ǂ��ɓ����I�ȋK�����������ނ̂ł��A�m�I�ɓ�����̔��f��������̂ł�����܂�
��B
�N������悤�Ȑ������̃C���[�W���ł��B�q�ǂ��ɓ����I�ȋK�����������ނ̂ł��A�m�I�ɓ�����̔��f��������̂ł�����܂�
��B
��Ȃ̂́A���I�Ȋւ����A�܂�z���͂����邱�ƂȂ̂ł��B�P�ƈ��A���ƕs���ɂ��Ă��A���I�ɋ����A����������
�N������悤�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B�܂������ȍs�ׁA���h�ȑԓx�A�܂��͕s���ȍs�ׂ̂��ꂼ��ɂӂ��킵������������
�āA�q�ǂ��̊���ɑi��������̂ł��B����ȑO�́A�搶���g���q�ǂ��̓����I�K�͂łȂ���Ȃ�܂���ł������A���͊�
�o�̌��ƌ��т����A���������Ƒz���͂ɓ��������Ă���C���[�W���q�ǂ��ɗ^���Ȃ���Ȃ�܂���B�v�t���܂łɓ�������
��ŎƂ߂���悤�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�q�ǂ�������ł�������Ɣ��f�ł���悤�ɂȂ�A�u����͑P�����Ƃ��A
�����ł���A����͈������Ƃ��A�ƂĂ��D���ɂȂ�Ȃ��v�A�ƌ�����悤�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ɣ����A����ɂ�锻
�f�A���ꂪ���������̊�b�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�N������悤�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B�܂������ȍs�ׁA���h�ȑԓx�A�܂��͕s���ȍs�ׂ̂��ꂼ��ɂӂ��킵������������
�āA�q�ǂ��̊���ɑi��������̂ł��B����ȑO�́A�搶���g���q�ǂ��̓����I�K�͂łȂ���Ȃ�܂���ł������A���͊�
�o�̌��ƌ��т����A���������Ƒz���͂ɓ��������Ă���C���[�W���q�ǂ��ɗ^���Ȃ���Ȃ�܂���B�v�t���܂łɓ�������
��ŎƂ߂���悤�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�q�ǂ�������ł�������Ɣ��f�ł���悤�ɂȂ�A�u����͑P�����Ƃ��A
�����ł���A����͈������Ƃ��A�ƂĂ��D���ɂȂ�Ȃ��v�A�ƌ�����悤�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ɣ����A����ɂ�锻
�f�A���ꂪ���������̊�b�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�l�Ԃ̎��ԑ́i�G�[�e���́j���ЂƂ̐��������炾�ł���A�����ł́A���ԓI�ɂ��ׂĂ��ւ�肠���Ă���A�Ƃ������Ƃ����@
�ł����Ȃ�A�������Ƃ��ɐ��������Ƃ��s�����Ƃ��ǂ�Ȃɑ厖�Ȃ��Ƃ��A������ł��傤�B�A������Ă�Ƃ��A�����ɉԂ��炩����
���Ƃ͂��܂���B�Ԃ��炭�̂́A�����Ƃ��ƂɂȂ��Ă���ł��B���߂͍��Â����Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ԃɂ��悤�Ƃ�����A�A
���͐����Ă�����܂���B���̐����ς�肩��v�t���܂ł̎q�ǂ��ɒm�I�ɓ������f�����߂悤�Ƃ�����A�A���̍����Ԃɂ���
���Ƃ���悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�܂������A�����ĉ����ĂȂ���Ȃ�܂���B����������A����̒��ł̓�������
�ł��B�q�ǂ��̊���̒��ɓ�������Ă܂��ƁA�v�t���ɂ����₩�Ȓm�����ڊo�߂�̂ł��B�����Ďq�ǂ��́A���̐����ς���
�v�t���̊ԂɊ���Ƃ��đ̌������������A�����œ��I�ɁA�m�I�ɐ[�߂āA�D�ꂽ�����I���f�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂�
���B
�ł����Ȃ�A�������Ƃ��ɐ��������Ƃ��s�����Ƃ��ǂ�Ȃɑ厖�Ȃ��Ƃ��A������ł��傤�B�A������Ă�Ƃ��A�����ɉԂ��炩����
���Ƃ͂��܂���B�Ԃ��炭�̂́A�����Ƃ��ƂɂȂ��Ă���ł��B���߂͍��Â����Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ԃɂ��悤�Ƃ�����A�A
���͐����Ă�����܂���B���̐����ς�肩��v�t���܂ł̎q�ǂ��ɒm�I�ɓ������f�����߂悤�Ƃ�����A�A���̍����Ԃɂ���
���Ƃ���悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�܂������A�����ĉ����ĂȂ���Ȃ�܂���B����������A����̒��ł̓�������
�ł��B�q�ǂ��̊���̒��ɓ�������Ă܂��ƁA�v�t���ɂ����₩�Ȓm�����ڊo�߂�̂ł��B�����Ďq�ǂ��́A���̐����ς���
�v�t���̊ԂɊ���Ƃ��đ̌������������A�����œ��I�ɁA�m�I�ɐ[�߂āA�D�ꂽ�����I���f�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂�
���B
��������͂��ׂāA���̂��Ƃ�ڂ����̂łȂ���Ȃ�܂���B����͐l���ɂƂ��đ�Ϗd�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B�A���̍�������
���ɉԂɂ��邱�Ƃ͂ł����A������肪�o�A�s���L�сA�Ō�ɉԂ��炭�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�������͓����̍���
����f�̒��ŁA�����ւ̋����̒��ŁA�������ƈ�ĂȂ���Ȃ�܂���B��������A�q�ǂ��͂��ƂɂȂ��āA�����̗͂�
���������m���Ɍ��т���ł��傤�B���̂Ƃ��A�����������A�����������Ȃ����������Ă��ꂽ�搶�ւ̎v���o�����������Ǝc
�邾���łȂ��A���̐����S�̂���сA�͂Â����A��N�ɂȂ��Ă��A�����I�Ȕ��f�����邽�тɁA�搶�̂��Ă̋������K�v��
�u�Ԃɖڊo�߂Ă����ł��傤�B�q�ǂ����Ȃ�炩�̓����I�ȕ����ɋ������Ă��A�悢���ʂ͓����܂���B���R�ɐ������鍰
�̒�����A�����I�ȕ��������̂��Ɛ����Ă���̂łȂ���Ȃ�܂���B��������A�q�ǂ��̍��́A�����I���f�͂����ł�
���A�����I�ȍs����g�ɂ��܂��B���ׂĂ��u���������_�v�ŋ��炷��悤�ɓw�߂邱�Ƃ��A����̗�w�I�ȕ��@�Ȃ̂ł��B����
���Ƃ͉��x�ł��J��Ԃ��Č���Ȃ���Ȃ�܂���B
���ɉԂɂ��邱�Ƃ͂ł����A������肪�o�A�s���L�сA�Ō�ɉԂ��炭�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�������͓����̍���
����f�̒��ŁA�����ւ̋����̒��ŁA�������ƈ�ĂȂ���Ȃ�܂���B��������A�q�ǂ��͂��ƂɂȂ��āA�����̗͂�
���������m���Ɍ��т���ł��傤�B���̂Ƃ��A�����������A�����������Ȃ����������Ă��ꂽ�搶�ւ̎v���o�����������Ǝc
�邾���łȂ��A���̐����S�̂���сA�͂Â����A��N�ɂȂ��Ă��A�����I�Ȕ��f�����邽�тɁA�搶�̂��Ă̋������K�v��
�u�Ԃɖڊo�߂Ă����ł��傤�B�q�ǂ����Ȃ�炩�̓����I�ȕ����ɋ������Ă��A�悢���ʂ͓����܂���B���R�ɐ������鍰
�̒�����A�����I�ȕ��������̂��Ɛ����Ă���̂łȂ���Ȃ�܂���B��������A�q�ǂ��̍��́A�����I���f�͂����ł�
���A�����I�ȍs����g�ɂ��܂��B���ׂĂ��u���������_�v�ŋ��炷��悤�ɓw�߂邱�Ƃ��A����̗�w�I�ȕ��@�Ȃ̂ł��B����
���Ƃ͉��x�ł��J��Ԃ��Č���Ȃ���Ȃ�܂���B
���������ƁA�F����͂��q�˂ɂȂ�ł��傤�B�u�q�ǂ������炷��Ƃ��A���̐����ς��Ǝv�t���Ƃ̊ԂɊ���ɂ�铹�����f���w
���A�m���ɑi����������A�K���ɏ]�킹����͂��Ȃ��A�ƌ����̂Ȃ�A���͉����m���Ȋ�����ĂȂ��Ȃ�B�v
���A�m���ɑi����������A�K���ɏ]�킹����͂��Ȃ��A�ƌ����̂Ȃ�A���͉����m���Ȋ�����ĂȂ��Ȃ�B�v
�����Ȃ̂ł��B���̎����������Ђ��A����搶�Ɛ��k�Ƃ̕s�m��v���ɂȂ��Ă����̂ł��B���̂��Ƃ��ЂƂ̗�Ŗ��炩�ɂ���
�݂܂��傤�B���͐l�Ԃ̍��̕s���ɂ��āA�q�ǂ��ɃC���[�W�Ő������悤�Ƃ��܂��B�Ȋw�I�ɂł͂Ȃ��A�C���[�W�ɂ���Ăł��B
�{���A�v�t���ȑO�̎q�ǂ��́A�Ȋw�ȂǑ��݂��Ă��܂���A���R�����_���A����������炾���ЂƂɌ��э��킳���Ă���
���B�ł�����A���̕s�����|�p�I�ɃC���[�W�ł���悤�Ɍ��̂ł��B�u���������A����͂��Ȃ�����B���͂��Ȃ����甇���o�Ă�
��ˁB����Ɠ����悤�ɁA�l�����ʂƁA�������炾���痣��āA�O�֏o�Ă�����v�B
�݂܂��傤�B���͐l�Ԃ̍��̕s���ɂ��āA�q�ǂ��ɃC���[�W�Ő������悤�Ƃ��܂��B�Ȋw�I�ɂł͂Ȃ��A�C���[�W�ɂ���Ăł��B
�{���A�v�t���ȑO�̎q�ǂ��́A�Ȋw�ȂǑ��݂��Ă��܂���A���R�����_���A����������炾���ЂƂɌ��э��킳���Ă���
���B�ł�����A���̕s�����|�p�I�ɃC���[�W�ł���悤�Ɍ��̂ł��B�u���������A����͂��Ȃ�����B���͂��Ȃ����甇���o�Ă�
��ˁB����Ɠ����悤�ɁA�l�����ʂƁA�������炾���痣��āA�O�֏o�Ă�����v�B
������邱�ƂŁA�q�ǂ��̑z���͂��h�����܂��B���������ƍ��̃C���[�W���q�ǂ��̓����S���h������悤�Ɏ����̂ł��B���̏�
���A��̂���������܂��B
���A��̂���������܂��B
���̂ЂƂ͂����ł��B�u���͈̂��搶���A���ł��悭�m���Ă���B�q�ǂ��͗c���A�����������Ă��Ȃ��B�q�ǂ��͂܂����̃��x��
�ɒB���Ă��Ȃ��̂�����A�q�ǂ��̃C���[�W�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃C���[�W�́A�����g�̖��ɂ͗����Ȃ�����ǂ��A�q��
���̖��ɂ͗��͂����v�B
�ɒB���Ă��Ȃ��̂�����A�q�ǂ��̃C���[�W�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃C���[�W�́A�����g�̖��ɂ͗����Ȃ�����ǂ��A�q��
���̖��ɂ͗��͂����v�B
�����������������l�����Ŏq�ǂ��ɐڂ����Ȃ�A���̃C���[�W���q�ǂ��̂�����ɑi�������邱�Ƃ͂���܂���B�����Ă����Ƃ��Ɠ�
���悤�ɁA�܂��O�ւ����Ă��܂������ł��B�搶�Ɛ��k�̊Ԃɂ́A�s�m��v���������Ă���̂ł�����A���̎����̂Ƃ�������
�Ȃ̂ł��B
���悤�ɁA�܂��O�ւ����Ă��܂������ł��B�搶�Ɛ��k�̊Ԃɂ́A�s�m��v���������Ă���̂ł�����A���̎����̂Ƃ�������
�Ȃ̂ł��B
�������A���͂����v�����Ƃ��ł��܂��B�u���Ƃ��Ǝ����͎q�ǂ���藘�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�������ӎ��̕���ł́A�����q�ǂ�
�̕��������ƌ����̂��낤�v�B�����q�ǂ��̂�����d���A�C���[�W�Ɋւ��Ă��A�u���������ł��������C���[�W��������̂ł͂�
���B���R���̂��̂������o���Ă��钱�̃C���[�W�����ɗ^���Ă��ꂽ�̂��B���͎q�ǂ��Ƃ܂������������炢�M�S�ɁA���̃C���[�W��
�M������v�B
�̕��������ƌ����̂��낤�v�B�����q�ǂ��̂�����d���A�C���[�W�Ɋւ��Ă��A�u���������ł��������C���[�W��������̂ł͂�
���B���R���̂��̂������o���Ă��钱�̃C���[�W�����ɗ^���Ă��ꂽ�̂��B���͎q�ǂ��Ƃ܂������������炢�M�S�ɁA���̃C���[�W��
�M������v�B
���������ŐM���Ă���Ƃ��A���̃C���[�W�͎q�ǂ��̂�����̒��ɏꏊ���߁A�������E�ɂł͂Ȃ��A�搶�Ɛ��k�̊Ԃɐ�����
����s�m��Ȃ��琸���Ȑ��E�̒��œ����n�߂�̂ł��B�����Ă����ɓ����s�m��v���������A�m�I�Ȏ��ƂŊw�K���邷�ׂĂ�
���铭�������Ă����̂ł��B
����s�m��Ȃ��琸���Ȑ��E�̒��œ����n�߂�̂ł��B�����Ă����ɓ����s�m��v���������A�m�I�Ȏ��ƂŊw�K���邷�ׂĂ�
���铭�������Ă����̂ł��B
�������Ďq�ǂ��͐搶�ׂ̗ŁA�̂т̂тƐ������Ă����܂��B���������搶�́A���k�̖T��ł����v���Ă��܂��B�u���͎q�ǂ�����
�̊��ɂȂ��Ă���B�q�ǂ����ł��邾�������Ŏ��������炷��@���p�ӂ��������S���Ă���B���k�������̕����̂���
���͂Ȃ��B�������N�������܂�Ă��������Ȃ̂�����v�B
�̊��ɂȂ��Ă���B�q�ǂ����ł��邾�������Ŏ��������炷��@���p�ӂ��������S���Ă���B���k�������̕����̂���
���͂Ȃ��B�������N�������܂�Ă��������Ȃ̂�����v�B
���ہA�搶�������̂��킯�ł͂���܂���B������A�����q�ǂ��̐����̋��͎҂ł��肳������悢�̂ł��B��t���A��
�̎���������Ƃ��A������Ԃ֒ʂ�����t�̗�����O���疳���ɑ��߂���͂��܂���B�A���̊��ɔz�����āA���t���悭��
���悤�ɂ��邾���ł��B����Ɠ����悤�ɁA�����ɂ��āA�q�ǂ��̓��Ȃ�͂����̂��Ɣ��B���Ă�����悤�ɂ���A�ǂ���
���ɂȂ��̂ł��B��������A���k�͗��h�Ɉ���Ă�����̂ł��B
�̎���������Ƃ��A������Ԃ֒ʂ�����t�̗�����O���疳���ɑ��߂���͂��܂���B�A���̊��ɔz�����āA���t���悭��
���悤�ɂ��邾���ł��B����Ɠ����悤�ɁA�����ɂ��āA�q�ǂ��̓��Ȃ�͂����̂��Ɣ��B���Ă�����悤�ɂ���A�ǂ���
���ɂȂ��̂ł��B��������A���k�͗��h�Ɉ���Ă�����̂ł��B
�������Ďq�ǂ��̂����낪���B���Ă����A�����S���A���Ɠ����悤�ɁA���X�ƈ��镔�����玟�̕����ւƐ����𐋂��Ă�����
���B�܂��A�����S�́A�͕�{�\�ƂȂ��Č���܂��B���ꂩ��A�O�q�����d���ŁA��������q�ǂ��̒��ɍ��Â��܂��B�����Ă���
�ɂȂ��āA������K�v�ȓ��I�ȁA�܂��͐g�̓I�ȗ͂����āA�����I�Ȑ��������ł���悤�ɂȂ�܂��B�����łȂ��ƁA������
���̗͑͂ƋC�͂���Ⴢ��Ă��āA���h�ȓ����I���f�͂ł��Ă��A����ɏ]�������̗͂����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��ł��傤�B
���B�܂��A�����S�́A�͕�{�\�ƂȂ��Č���܂��B���ꂩ��A�O�q�����d���ŁA��������q�ǂ��̒��ɍ��Â��܂��B�����Ă���
�ɂȂ��āA������K�v�ȓ��I�ȁA�܂��͐g�̓I�ȗ͂����āA�����I�Ȑ��������ł���悤�ɂȂ�܂��B�����łȂ��ƁA������
���̗͑͂ƋC�͂���Ⴢ��Ă��āA���h�ȓ����I���f�͂ł��Ă��A����ɏ]�������̗͂����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��ł��傤�B
���E���N���Ɏ�{���͋������������Ă�����A�����S����������ƍ��Â��܂��B���̐����ς�肩��v�t���܂łɑP�ւ̋���
�̗͂ƈ��ւ̔����̗͂��q�ǂ��̊���̒��Ő����Ă���Ȃ�A��N�ɂȂ��āA�����I�ȑԓx���Ƃ点�܂��Ƃ��邠�ꂱ��̗}
�������z����͂������Ƃ��ł���Ƃł��傤�B
�̗͂ƈ��ւ̔����̗͂��q�ǂ��̊���̒��Ő����Ă���Ȃ�A��N�ɂȂ��āA�����I�ȑԓx���Ƃ点�܂��Ƃ��邠�ꂱ��̗}
�������z����͂������Ƃ��ł���Ƃł��傤�B
�͕킷�鑶�݂������Ƃ��̐l�Ԃ́A���炾�̒��ɍ��ɕK�v�ȗ͂�~���܂����B���̗͂ɂ���āA���E���N���ɂȂ�ƁA������
��A�����A�����̗͂�����Ă��܂����B�����đ�O�E���N���ɁA�q�ǂ��͂̂т̂тƌ������Ȃ���A�܂莩���̒m����
�����I�Ȕ��f��������悤�ɂȂ�̂ł��B���傤�Ǒ��z�̌��ɉ����ĐA�����Ԃ��J���A�������Ԃ悤�ɂł��B���E���N���̂���
���Ƒ��E���N���̂�����̒��ŁA�����̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ���̂��A���傤�ǐA���̉Ԃ��J���A��������悤�ɁA���R�ɐl����
���邽�߂ɖڊo�߂�̂ł��B
��A�����A�����̗͂�����Ă��܂����B�����đ�O�E���N���ɁA�q�ǂ��͂̂т̂тƌ������Ȃ���A�܂莩���̒m����
�����I�Ȕ��f��������悤�ɂȂ�̂ł��B���傤�Ǒ��z�̌��ɉ����ĐA�����Ԃ��J���A�������Ԃ悤�ɂł��B���E���N���̂���
���Ƒ��E���N���̂�����̒��ŁA�����̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ���̂��A���傤�ǐA���̉Ԃ��J���A��������悤�ɁA���R�ɐl����
���邽�߂ɖڊo�߂�̂ł��B
�����I�Ȋϓ_����A���I�ɁA���R�ɁA�������g��]���ł���悤�ɂȂ�ƁA��������l�Ԃ̓��ʂƌ��т��܂��B�����āu����
�͎������g�̖�肾�v�A�Ǝv����悤�ɂȂ�܂��B���炾�̌��t�z����͂������̖��ł���悤�ɁA������p�⓹����
�������̖��ɂȂ�̂ł��B�����̖{�\���S�g���A�畆�̕\�ʂɎ���܂Ŋт������Ă���悤�ɁA�����𐳓��Ȏd���Ŏ�����
���ɔ��B�����Ă����l�́A���̓����������̂��̂Ɗ����Ƃ��Ă���̂ł��B
�͎������g�̖�肾�v�A�Ǝv����悤�ɂȂ�܂��B���炾�̌��t�z����͂������̖��ł���悤�ɁA������p�⓹����
�������̖��ɂȂ�̂ł��B�����̖{�\���S�g���A�畆�̕\�ʂɎ���܂Ŋт������Ă���悤�ɁA�����𐳓��Ȏd���Ŏ�����
���ɔ��B�����Ă����l�́A���̓����������̂��̂Ɗ����Ƃ��Ă���̂ł��B
����������A�ǂ��Ȃ�ł��傤���B����������A�l�Ԃ͎����Ɍ������Ă���������悤�ɂȂ�̂ł��B�u���������I�łȂ��Ȃ�����A��
�͎����̒��̑厖�Ȃ��̂����������ƂɂȂ�v�B
�͎����̒��̑厖�Ȃ��̂����������ƂɂȂ�v�B
���炾�̈ꕔ���������l�́A�����̒��̑厖�Ȃ��̂��������Ǝv���܂��B�O�q�����Ӗ��Ŏ����̒��ɓ����̗͂���Ă��l�́A
�u�����������̂āA�Љ�I�ȍs�����Ɍ��т��Ȃ��Ȃ�A���͎����̑�ȕ����������Ă���v�A�Ɗ�����悤�ɂȂ�̂�
���B
�u�����������̂āA�Љ�I�ȍs�����Ɍ��т��Ȃ��Ȃ�A���͎����̑�ȕ����������Ă���v�A�Ɗ�����悤�ɂȂ�̂�
���B
�����������I�łȂ���A�����̒��̑�Ȃ��̂������Ă���A�Ɣ��f�ł��邱�Ƃ́A���������l�Ԃ������̒��ɔ��B�����邱
�Ƃ̂ł���ł����͂ȓ����Փ��Ȃ̂ł��B�l�Ԃ𐳂�������ł����Ȃ�A���̐l�́u�S�l�v�ł��肽���Ǝv���A���R�Ɏ����̓���
�S�ɗ�܂���āA�����̒��Ɂu�쐫�v�����߂�悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�A�̓��Ɏ��R�̗͂������Ă���悤�ɁA���E���т���
�����P�������������̒��ɂ������Ă���̂�m��悤�ɂȂ�܂��B
�Ƃ̂ł���ł����͂ȓ����Փ��Ȃ̂ł��B�l�Ԃ𐳂�������ł����Ȃ�A���̐l�́u�S�l�v�ł��肽���Ǝv���A���R�Ɏ����̓���
�S�ɗ�܂���āA�����̒��Ɂu�쐫�v�����߂�悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�A�̓��Ɏ��R�̗͂������Ă���悤�ɁA���E���т���
�����P�������������̒��ɂ������Ă���̂�m��悤�ɂȂ�܂��B
��g�I�Ɍ����Ȃ�A�����ɒ��S������Ƃ��܂��B���S�Ƃ��č��ꂽ�S�ł��B�����ɒN�������Ă��������܂��B�u���̒��S�͎���
�ɂ��g����B�S�ɂ͂��������͂����݂��Ă���v�B
�ɂ��g����B�S�ɂ͂��������͂����݂��Ă���v�B
�����������ɕʂ̐l�����āA���������܂��B�u�������āB���S�����ɂȂ���āB����Ȃ��Ƃ��ǂ��ł������B���̒��S�͎���
�n�p�̂��̂Ȃ̂�����v�B
�n�p�̂��̂Ȃ̂�����v�B
�l���S�̂̒��ɁA���܂��܂Ȕ��B�ߒ���ʂ��āA�����̗쐫�������Ă���̂����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�́A���Ƃ��痈���l�Ɏ���
���܂��B�l�Ԃ̒��ɗ쐫�̓��������Ȃ��ŁA�S�����̓���Ƃ��Ă������Ă��Ȃ����̐l�́A���������̔n�ɑł������
�S�ł���Ƃ����l���Ă��܂���B���������l�́A�q�ǂ��ɐl���̐�����������������̂ł��A�l���𐳂���������͂���Ă�̂�
������܂���B�l���̂��߂ɓ�������I�ȈӖ��Ŋ������A�ӎu�����Ȃ�A���̓����̗͍͂ł��͋����Љ�Փ��ɂ��Ȃ肤
��̂ł��B
���܂��B�l�Ԃ̒��ɗ쐫�̓��������Ȃ��ŁA�S�����̓���Ƃ��Ă������Ă��Ȃ����̐l�́A���������̔n�ɑł������
�S�ł���Ƃ����l���Ă��܂���B���������l�́A�q�ǂ��ɐl���̐�����������������̂ł��A�l���𐳂���������͂���Ă�̂�
������܂���B�l���̂��߂ɓ�������I�ȈӖ��Ŋ������A�ӎu�����Ȃ�A���̓����̗͍͂ł��͋����Љ�Փ��ɂ��Ȃ肤
��̂ł��B
���݁A�������͎Љ���̊����f���ē����Ă��܂��B���̎Љ���̖������������͊m�M���Ă��܂��B����ɂ��Ă��b�ł�
��悩�����̂ł����A�������A���ɗ^����ꂽ���Ԃ͂����I���܂��B�ł�����ȒP�ɁA���̂��Ƃ�����\���グ�����̂ł��B
��悩�����̂ł����A�������A���ɗ^����ꂽ���Ԃ͂����I���܂��B�ł�����ȒP�ɁA���̂��Ƃ�����\���グ�����̂ł��B
�Љ���ɂ͑����̑��ʂ�����܂��B���ݖ��}�h�w�̒N�����A�Љ������̓I�Ɏ��グ�A�Љ�̖����̂��߂ɎЉ���v
���l���A���s�Ɉڂ����Ƃ���Ƃ��A���̉��v�̍ו�����������K�v�ɔ����܂��B�������A�l���A���s�Ɉڂ����Ƃ̂ł���Љ
���x�̂��ׂĂɑ��ẮA�������킴������Ȃ��̂ł��B�u�������Ȃ��ɎЉ���������̂́A�܂�Ō��̂Ȃ����������Ă悤
�Ƃ��Ă���悤�Ȃ��̂��B���̂Ȃ������ŁA��ЂƂ��̂������悤�Ƃ��Ă���悤�Ȃ��̂��v�B
���l���A���s�Ɉڂ����Ƃ���Ƃ��A���̉��v�̍ו�����������K�v�ɔ����܂��B�������A�l���A���s�Ɉڂ����Ƃ̂ł���Љ
���x�̂��ׂĂɑ��ẮA�������킴������Ȃ��̂ł��B�u�������Ȃ��ɎЉ���������̂́A�܂�Ō��̂Ȃ����������Ă悤
�Ƃ��Ă���悤�Ȃ��̂��B���̂Ȃ������ŁA��ЂƂ��̂������悤�Ƃ��Ă���悤�Ȃ��̂��v�B
�Љ���́A�������������̒��ɐ��������Ƃ���Ƃ����߂āA�������l�@�ΏۂɂȂ�̂ł��B�l����S�̓I�Ȋ֘A�̉��ɍl
�@����Ȃ�A�������킴������܂���B�u�������́A�Љ�����Ƃ炷���ɓ������B�Љ���́A�^�̈Ӗ��ŁA��I�Ȋϓ_��
���ɒu����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B
�@����Ȃ�A�������킴������܂���B�u�������́A�Љ�����Ƃ炷���ɓ������B�Љ���́A�^�̈Ӗ��ŁA��I�Ȋϓ_��
���ɒu����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B
�ł�����A�Љ�����A�������ɂǂ����������̂����A�܂�����܂��B�����́A���������l�q�w�I��w�ƌĂԗ쐫�̊w
���A���̈Ӗ��ł��A����̑傫�Ȏ�����ɐ����Ɍ��������A�����Ď��������������Ƌ��ɓ����I�Ȑl�Ԃ��琬���邽�߂�
����ɐ^���Ɋւ���Ă��邱�Ƃ��������Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă���܂��B(P119-P127)
���A���̈Ӗ��ł��A����̑傫�Ȏ�����ɐ����Ɍ��������A�����Ď��������������Ƌ��ɓ����I�Ȑl�Ԃ��琬���邽�߂�
����ɐ^���Ɋւ���Ă��邱�Ƃ��������Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă���܂��B(P119-P127)